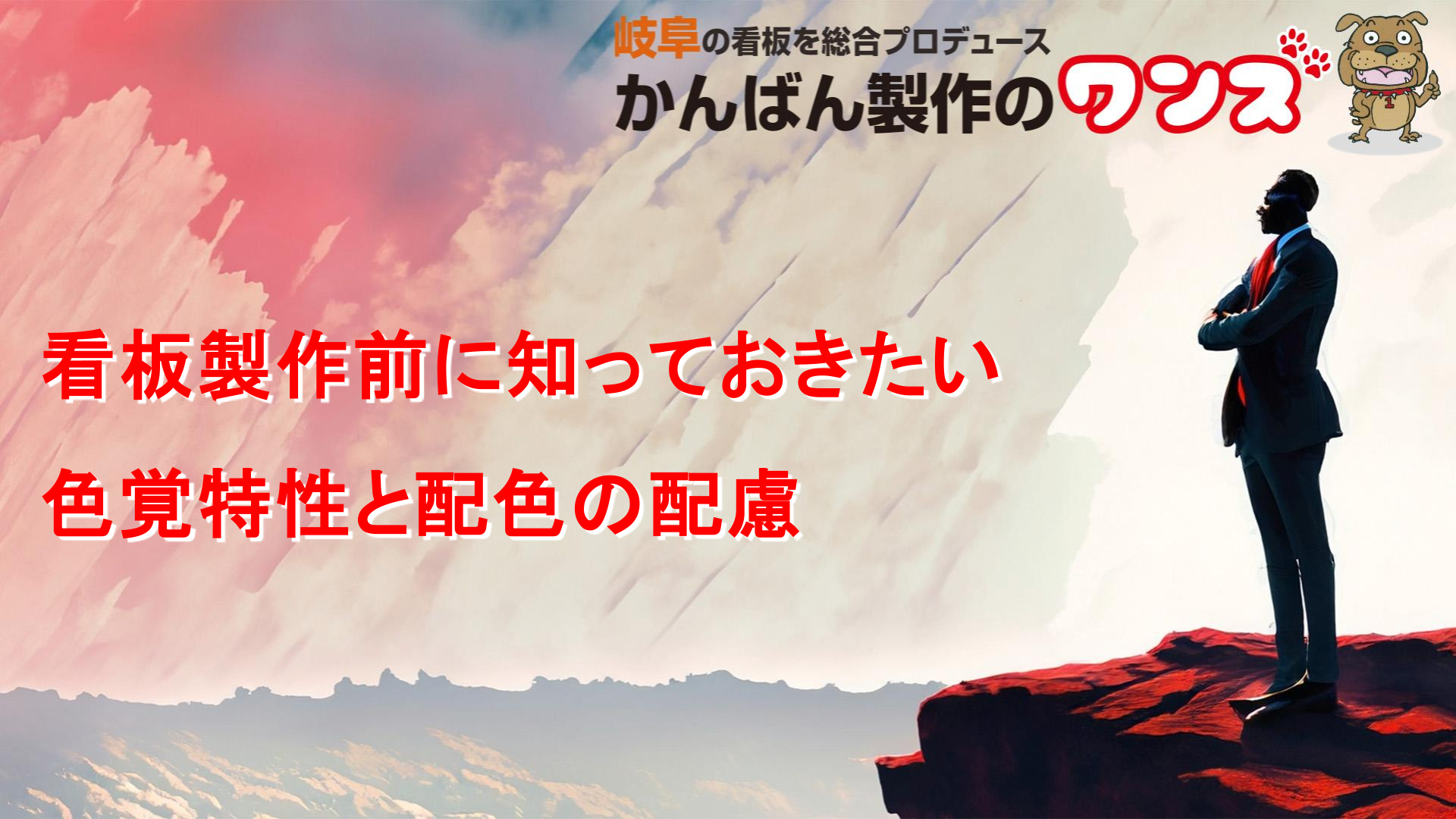
不特定多数の人が行き交う街中では、看板を目にする人の特性も多種多様です。人間の目の見え方も一定ではなく、デザインの検討に際しては、さまざまな色覚特性への配慮を行う必要があるでしょう。誰にでも優しいユニバーサルデザインは、企業の信頼性やイメージ向上にもつながるものです。この記事では、より多くの顧客に寄り添うことができる看板デザインのポイントについて解説します。
◇色覚多様性(D型・N型)に配慮した基本指針
看板製作において、色覚の多様性に配慮したデザインはもはや「特別な配慮」ではなく、徐々に「基本知識」となりつつあります。ここでは、D型(赤緑色覚特性)とN型(一般色覚)の双方に配慮した看板製作の基本指針をご紹介します。
◎色覚多様性の理解:D型とN型の見え方の違い
色覚特性は個人によって大きく異なりますが、特に看板デザインで配慮が必要なのが「赤緑色覚特性」(D型)。日本では男性の約5%、女性の約0.2%が該当するとされ、決して稀な特性ではないのです。
D型の方は、赤と緑の区別が難しく、この2色が似た明るさや彩度の場合、ほぼ同じ色に見えてしまいます。例えば、赤い文字と緑の背景の組み合わせは、コントラストが低く読みづらい可能性が高いです。
一方、N型(一般色覚)の方は、色の区別が比較的容易ですが、だからといって全ての色の組み合わせが適切というわけではありません。全てのユーザーにとって見やすいデザインを心がけることが重要です。
◎配慮すべき配色の基本原則
色の組み合わせに頼りすぎない
情報を色だけで伝えないことが最も大切な原則です。特に「赤と緑」「緑と茶」「ピンクと灰色」「青と紫」の組み合わせは、D型の方には区別が難しいので、注意しましょう。
明度差を十分につける
色相に頼るのではなく、明度差を大きくすることで、色覚に関わらず認識しやすくなります。白と黒のコントラストが最も判別しやすいのは、この明るさの差が極めて大きいためです。
形や模様の併用
色に加えて、ロゴや模様、アイコンを併用することで、情報を多重化できます。例えば、グラフでは色分けだけでなく、斜線やドットなどのパターンも併用すると良いでしょう。
十分なサイズとスペース
小さなデザインは、どんな色覚の人にも判別が難しくなります。重要な情報は、十分なサイズで表示し、余白を適切に確保しましょう。
◎実践的なチェック方法
グレースケール変換
デザインを一度グレースケール(白黒)に変換して確認することで、明度差が十分かどうかをチェックできます。色の違いがなくても情報が伝わるかどうかは大切な判断基準です。
色覚シミュレーションツールの活用
現在では、多くのデザインツールに色覚シミュレーション機能が搭載されています。D型の方の見え方を事前に確認しておくと、配色の問題を未然に防げます。
◇コントラスト比と明度差で可読性を確保
誰にでも見やすい看板を作る上で重要なのは「コントラスト」や「明度差」と先ほどもお伝えしましたが、具体的にどれくらいの明度差があれば十分なのか、分からない方も多いでしょう。以下ではこれらの基準に焦点を当て、具体的な確保方法を解説します。
◎コントラスト比の基本と基準値
コントラスト比は、文字と背景の明るさの差を数値化したもので、WCAG(Webコンテンツアクセシビリティガイドライン)では明確に基準が定められています。看板製作でもこの考え方は応用可能ですので、確認しておきましょう。
基準となるコントラスト比:
- AAレベル(最低限満たすべき基準): 4.5:1以上
- AAAレベル(より高い基準): 7:1以上
例えば、白(明度100%)と黒(明度0%)の組み合わせのコントラスト比は21:1であり、非常に高い視認性を持つと言えます。逆に、薄い灰色同士の組み合わせでは、コントラスト比が3:1以下になることもあり、読みづらくなります。
看板は多くが屋外での使用を想定されるため、日光の影響を考慮し、より高いコントラスト比を目指すことが推奨されます。
◎明度差の重要性と測定方法
色覚特性に関わらず、人は明度差によって形や文字を認識するものです。D型(赤緑色覚特性)の方にとって、明度差は色の違いよりもはるかに効果的です。
明度差の確保方法:
- HSBカラーモデルの活用: デザインツールのHSB(色相・彩度・明度)モードを活用し、明度(Brightness)の値を調整します。文字と背景で明度値の差を30以上確保することを目安としましょう。
- グレースケール変換チェック: デザインをモノクロに変換した際に、情報が正しく伝わるか確認します。色の違いがなくても区別できるのが理想です。
- シミュレーションツールの活用: 前章でも紹介した色覚シミュレーションツールで、明度差が十分か検証します。
◎実践的な調整テクニック
色相に頼らない安全な組み合わせ
- 黒/白、黒/黄色、白/紺など、伝統的に看板で使われてきた組み合わせは、明度差が大きく失敗が少ないです。
- パステルカラー同士の組み合わせはおしゃれですが、視認性の観点からはなるべく避け、明るい色と暗い色を組み合わせます。
彩度と明度のバランス
- 同じ明度でも、彩度の高い色はより目立ちます。重要情報には高彩度色を使用すると良いでしょう。
- 彩度だけに頼るのではなく、必ず明度差も確保します。
境界線や影の効果的活用
- 色の境界がわかりづらい場合は、文字に縁取り(境界線)を追加するとコントラストが向上します。
- シャドウをつけることで、背景から浮き立たせる方法もあります。
◇NG配色の回避とテクスチャ・アウトライン代替
これまで色覚多様性の基本とコントラストの重要性について学んできました。以下では、具体的に避けるべき配色と、色に依存しない情報伝達のテクニックであるテクスチャやアウトラインの活用方法を詳しく解説します。
◎避けるべきNG配色とその理由
色覚特性に関わらず判別が難しい配色があります。看板の目的を損なうリスクがあるので、特に以下の組み合わせには注意しましょう。
主なNG配色パターン:
- 赤と緑の組み合わせ: D型の方にはほぼ同色に見えることが多く、最も避けるべきパターンです。信号機のように「止まれ」と「進め」といった合図を色で表現する場合は、位置や形状で区別できるデザインが不可欠です。
- ピンクと灰色/薄い緑: 赤と緑のように、明度が近い場合、区別が極めて困難になる組み合わせです。
- 青と紫の組み合わせ: 暗い環境では違いが分かりづらくなります。看板の照明条件を考慮する必要があるでしょう。
- 緑と茶色: 自然を連想させる配色ですが、色覚によっては同系色に見えてしまいます。
これらの配色を使用する場合は、必ず明度差を大きくする、境界線を追加するなどの対策をセットで検討しましょう。
◎テクスチャや模様の効果的活用
色の代わりに、または色と併用してテクスチャ(模様)を活用すると、情報を確実に伝えられるようになります。
具体的な活用例:
- グラフやチャート: 隣接する箇所に斜線、ドット、格子模様などの異なるパターンを適用します。色の違いがわからなくても、模様の違いでデータを区別できます。
- 地図や案内図: エリア分けには色だけでなく、模様を併用します。例えば、商業地域は斜線、住宅地域はドット模様などで表現すると、より明確になります。
テクスチャは、色の違いを補完する強力なツールですが、複雑すぎるとかえって見づらくなるので注意。シンプルで明確な模様を選ぶことが重要です。
◎アウトラインや形状を利用した代替表現
色による識別に依存しない、もう一つの効果的な方法がアウトライン(輪郭線)や形状の差異です。
実践的なアプローチ:
- 文字の縁取り:文字に反対色の縁取りを追加することで、可読性が飛躍的に向上します。代表的なものとして、白文字に黒の縁取りは、どんな背景色にも有効です。
- 形状の差異化: 色で区別している要素に、異なる形状を割り当てます。
- 太さやサイズの違い: 線の太さや要素のサイズに差をつけることでも、違いを明確に表現できます。
◇まとめ
色覚多様性に配慮した看板製作は、特定の人のためだけでなく、全てのユーザーにとって見やすいデザインになるものです。本記事で紹介した基本指針を参考に、誰しもに優しく寄り添える看板を目指してみてください。






