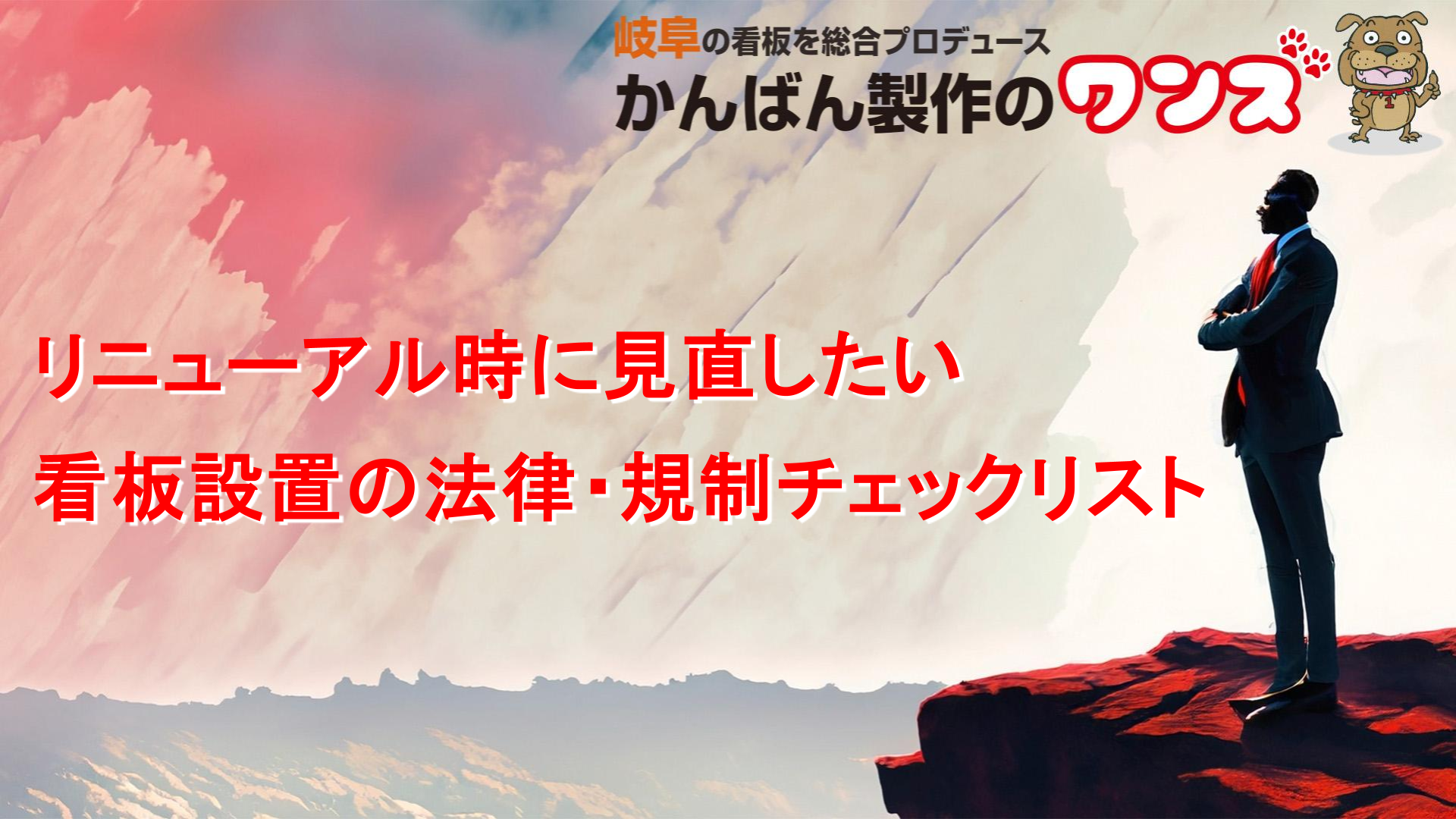
店舗のリニューアル時に、看板も新しくしたいと考える方は多いでしょう。看板の設置に際しては、当然ですが法律や規制を巡視して施工する必要があります。古くからあった店舗の場合は、開店当初から法律などが変わっている可能性があるので、深く考えずに設計すると後々後悔する可能性も。この記事では、看板設置の前に見直しておくべき法律や規制をまとめました。
◇屋外広告物条例の基本と区域規制の確認
看板や広告塔を新しく設置またはリニューアルする際には、知っておくべき法律や条例がいくつかあります。特に「屋外広告物条例」は、良好な景観の形成や維持、公衆への迷惑防止を目的としており、看板設置において基本かつ重要な規制です。ここでは、屋外広告物条例の基本と、看板設置に大きく関わる「区域規制」について解説します。
◎屋外広告物条例の基本目的と対象
屋外広告物条例とは、屋外広告物法に基づいて都道府県や政令指定都市などが定める条例です。その目的は、良好な景観の形成と風致の維持、そして公衆の防止です。
「屋外広告物」とは、看板、はり紙、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものと定義されます。つまり、店舗の看板だけでなく、のぼり旗や貼り紙なども対象となる可能性があります。
屋外広告物を設置するためには、原則として設置前に許可を受ける必要があります。無許可で設置したり、条例に不適格な広告物を設置したりした場合、是正命令や罰則の対象となることがあります。
◎規制の種類を理解する:禁止区域・禁止物件・許可区域
屋外広告物条例による規制は、大まかに以下の3つに分けられます。これらを知っておくことが、適切な看板設置への第一歩です。
1.禁止区域
良好な景観や風致を維持するため、屋外広告物の表示が原則として禁止されているエリアです。例えば、以下のような地域が該当します。
- 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域
- 景観地区、風致地区、特別緑地保全地区
- 公園、緑地、運動場、河川、社寺・墓地の境域
- 学校、病院、図書館、美術館、官公署などの敷地
- 道路や鉄道の路線敷地およびそれらに接続する地域
2.禁止物件
広告物を設置することが禁止されている物件です。例えば、橋や高速道路、高架鉄道、道路標識、信号機、ガードレールなどが該当します。
3.許可区域
禁止区域に該当しない場合でも、行政ごとに許可区域が設定されており、屋外広告物を設置するには許可が必要です。許可を得るためには、広告物の種類や設置する地域に応じて、大きさ、形状、色彩などの基準を満たす必要があります。
◎リニューアル前にすべき区域確認のポイント
看板を新設またはリニューアルする際は、まずお店や事業所の所在地がどのような区域に該当するのかを確認することが最重要です。
- 用途地域を確認する: お店の立地が「第一種低層住居専用地域」などの禁止区域に該当しないかをまず確認しましょう。
- 禁止物件に設置していないか確認する: 看板を設置しようとしている建物や工作物自体が、禁止物件に該当しないかも確認が必要です。
- 相談窓口を利用する: 区域や規制の判断が難しい場合や、詳細を確認したい場合は、お近くの自治体の屋外広告物担当窓口に問い合わせることを強くお勧めします。申請前の相談を受け付けている場合がほとんどです。
◇サイズ・高さ・照明・点滅に関する制限事項
上記した法律や条例の順守のため、デザインや訴求効果だけでなく、「サイズ(面積)」「高さ」「照明」「点滅」 に関する制限を理解することは極めて重要です。これらは、景観形成や交通安全、近隣の居住環境に直接関わるため、比較的厳しく規制される傾向があります。本章では、これらの制限事項の概要と確認ポイントを解説します。
◎面積(サイズ)と高さの制限 – 地域や設置場所で異なる基準
看板の面積や高さのルールは、その看板が設置される「エリア」や「設置方法」によって細かく定められています。これらは、良好な景観の形成や、視認性による交通への影響を考慮したものです。
面積の制限
- 壁面看板:多くの場合、その壁面面積の一定比率(例えば三分の一)以下という規制があります。また、商業地域とそれ以外のエリアでは、看板一面あたりの最大面積が異なり、商業地域の方がより大きな看板が許可される傾向があります。
- 自己用広告物(自家用広告物):自身の店舗や事業所に自分自身の広告を出す場合、一定の面積までは許可が不要な「適用除外」となることも。この面積は、規制の厳しい地域(例えば住居専用地域)ほど小さく設定されています。
高さの制限
- 地上設置型の看板(広告塔・広告板):地上から看板の上端までの高さが10m以下という規制が一般的です。
- 屋上看板:建築物の屋上に設置する看板のサイズは、地盤面からの建築物の高さの2/3以下など、建物の高さに応じた制限や、絶対的な高さの上限が設けられています。
- 突出看板:歩行者や通行車両の安全を確保するため、看板の下端の高度や道路境界線からの突出し(出幅)の限度が定められています。
◎照明の制限 – 眩しさや景観への配慮
看板の照明や色彩は視線を引きやすいため、夜間の景観や、運転者・歩行者の通行、地域の雰囲気に負の影響を与えないよう規制されています。
照明に関する制限
- 点滅光の禁止:信号機や交通標識と誤認されるおそれがあるため、点滅する光源の使用は原則として禁止されている自治体が多いです。
- 減光措置:深夜の時間帯は照明を消すか、光度を大幅に下げることを義務付ける条例もあります。
- 投光器の方向:看板を照らす投光器が、近隣の住宅や道路、夜空に向かないよう設置方向が制限される場合があります。
◇道路占用・境界・私有地の取り扱いルール
これまでさまざまな規制について説明しましたが、さらに「道路占用」「境界線」「私有地」 に関するルールを理解しておくことで、トラブルを防ぎ、円滑に作業を進めることができます。ここでは、これらの重要なポイントを解説します。
◎道路占用の基本と申請の流れ
看板を道路やその上空などで継続して使用する行為は 「道路占用」 とみなされ、道路管理者の許可が必要となります。これは、道路の本来の目的である交通機能や安全性を確保するためのルールです。
道路占用の具体例
- 広告看板やのぼり旗の設置
- 工事用の仮囲いや足場の設置
- 宅地への乗入口の設置
申請の主な流れ
- 事前相談: 物件や場所によって制限があるため、まずは自治体の担当窓口に相談しましょう。
- 申請書の提出: 申請書には、案内図、平面図、立面図などの添付書類が必要。処理期間は2〜3週間程度かかる場合が多いため、余裕をもって申請しましょう。
- 占用料の納付: 許可が下りると、占用物件や面積、期間に応じた占用料が発生します。占用料は各自治体の条例に基づいて計算されます。
◎私有地内の看板でも許可が必要な場合
看板を私有地内に設置する場合でも、それが屋外広告物に該当すれば、条例に基づく許可が求められます。
- 「私有地だから自由」ではない: 冒頭で述べたように屋外広告物条例は、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する迷惑の防止を目的としており、対象となる広告物が私有地内にあるかどうかは問いません。
- 許可申請の相談先: 許可申請や相談は、多くの場合、お店や事業所を構える市町村の担当課で受け付けています。
◎境界確認と近隣への配慮
看板の設置、特に基礎部分を作る場合や、建物の壁面に取り付ける場合は、土地の境界線や近隣への影響に細心の注意を払う必要があります。
- 境界線の確認: 看板やその基礎が隣地にかかっていないか、越境していないかを必ず目視しましょう。境界を越える場合は隣地所有者の承諾が必要になる可能性も。
- 近隣への影響への配慮: 看板の光が隣家に直接入らないよう配慮し、風圧や落下のリスクがないか確認するなど、近隣トラブルが起こらないようにすることが重要です。
◇まとめ
看板はお店や企業の顔です。ルールを守って設置することは、地域への配慮を示し、結果的にブランドの信頼性を高めることにもつながります。リニューアルを良い機会とし、これらのポイントをしっかりと見直してみてください。道路や隣地との境界、私有地におけるルールなど様々な制限があるので、記事を参考にしつつ、必要に応じて専門家や自治体の担当窓口に相談しましょう。






