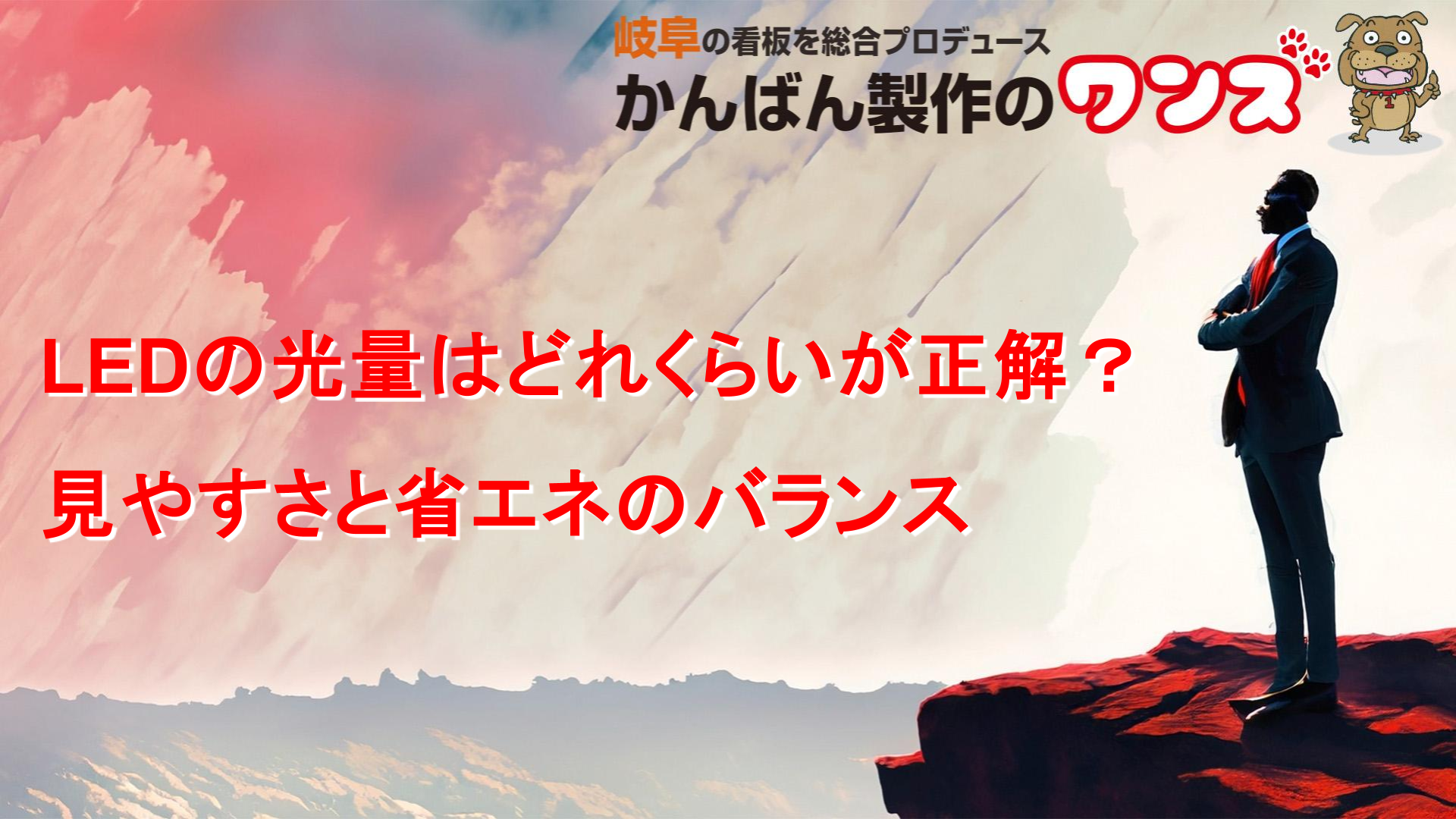
看板は24時間働いてくれる広告媒体です。しかし、ただ設置するだけでは、夜間に十分な効果を発揮できない可能性があります。暗い中でも視認性を確保するためにはLEDなどの照明が必要ですが、初めて設置する場合は光量に悩む方もいらっしゃると思います。この記事では、見やすさと省エネを両立するための照明計画について解説します。
◇照度と輝度の基礎(lx/cd・cd/m²)を理解する
照明の明るさを考える上で、数値的な基準となる照度と輝度について知っておきましょう。下記に、二つの指標についてまとめました。
◎看板の「見やすさ」を測る二つの指標
看板のLEDを選ぶ際、「どれくらい明るければ良いのか?」と悩まれたことはありませんか?その答えを見つける鍵が、「照度(lx:ルクス)」と「輝度(cd/m²:カンデラ毎平方メートル)」という二つの指標です。これらを理解することは、効果的で省エネな看板作りにおける最初の一歩。どちらも光の強さに関連する単位ですが、実は全く異なる概念を表しているのです。
◎照度(lx)と輝度(cd/m²)の違いとは?
・照度(lx) は、「モノの表面に当たる光の量」を表すものです。単位はルクス(lx)で、照明の設計などでよく使われます。簡単に言えば、看板を「照らす側」の明るさの指標です。officeのデスク上は約500lx、晴れた屋外は10,000lx以上になります。
・輝度(cd/m²) は、「モノの表面から発せられる(または反射する)光の強さ」、つまり「人間の目が実際に感知する明るさ」そのものを指します。単位はカンデラ毎平方メートル(cd/m²)またはニト(nit)です。スマートフォンのディスプレイは約500~1,000cd/m²、屋外看板は5,000cd/m²以上が必要とされることもあります。
基本的にLED看板の「見やすさ」に直接関わるのは輝度です。どれだけ強い光で照らしても(照度が高くても)、看板の素材や表示内容によって反射する光の量(輝度)は異なるので、見え方は変わってくるのです。
◎適切な数値選びが省エネへの第一歩
この二つの関係を理解すると、無駄な光量を抑えた、最適な「見やすさ」の実現に近づきます。
必要以上に照度(ルクス)を高くしてしまうと、電力の浪費に直結します。まずは設置環境(屋内/屋外、周囲の明るさ)を正しく把握し、必要な輝度(cd/m²)の大まかな目標を立てましょう。その目標輝度を実現するために、必要なLEDの光量(=照度)を逆算して設定することが、見やすさと省エネの完璧なバランスを取る秘訣です。
◇道路環境別の推奨光量(住宅地・幹線・商業地)
指標としての概念を理解出来ても、実際にどれくらいの数値にすべきかは悩むところでしょう。推奨される光量は環境によって大きく左右されるものです。ここでは、設置する環境別の推奨光量をご紹介します。
◎住宅地のLED看板:静かな居住環境との調和
住宅地に設置するLED看板では、「適切な明るさ」と「生活環境への配慮」の両立が課題です。過剰な明るさは住民の安眠を妨げる光害(ひかりがい)となり、トラブルになることも。そのため、住宅地域では輝度を300~500 cd/m²程度に抑えることが推奨されます。周辺住宅への窓面照度を約2 lx以下に抑制して、不快な眩しさを最小限に留めることが目標です。
光源の色温度も重要です。落ち着いた暖色系(3000K以下)の光は、住宅地の穏やかな雰囲気に調和しやすく、睡眠への悪影響が冷色系光より小さいとされています。タイマーや調光器を用いて深夜帯は輝度を低下させるなどの配慮があれば理想的です。
◎幹線道路のLED看板:高速走行車への明確な視認性
幹線道路は、高速で移動する車両の運転者に対し、「一瞬で正しく情報を伝える」ことが要求される環境です。ここでは、住宅地よりも高い輝度が必要となります。一般的に、主要な幹線道路では、輝度は5,000 cd/m²以上が推奨されます。高速走行時の短い視認時間や、太陽光・ヘッドライトといった競合光の中でも視認性を確保するためです。
視認性を高めるためには輝度だけではなく、コントラストの高さも重要です。背景の明るさや看板の色味を考慮しつつ、文字と背景の明度差を十分に確保しましょう。
省エネの観点からは、高い輝度を確保しつつ、必要以上に光量を上げないことが大切です。LEDの高効率特性を活かし、特定の時間・必要な場所に最適な光を照らす「スマート照明制御」の導入が有効です。例えば、交通量が激しい時間帯は明るくし、深夜帯は輝度を落とす調光機能などを採用することで、省エネと視認性の両立を図れます。
◎商業地のLED看板:活気ある集客と景観形成のバランス
商業地は、集客を目的とし、夜間もにぎわいを見せるエリアです。ここでは、「人の注目を集めるデザイン性」と、「歩行者が不快に感じない快適性」のバランスが鍵となります。推奨される輝度は2,000~3,000 cd/m²程度。この輝度は、周囲の店舗照明や街頭照明よりも目立ちつつ、歩行者にとって過度に眩しいとは感じない範囲とされています。
◇光害・景観条例への配慮(岐阜エリアの注意点)
光害(ひかりがい)とは、「照明の設置方法や配光が不適切なため、景観や周辺環境にもたらす悪影響」を指します。岐阜県は、雄大な自然と歴史ある町並みという貴重な景観資源を守るため、景観条例を制定しており、屋外広告物(看板)に対しても配慮が求められています。ここでは、岐阜エリアでLED看板を設置・設計する際に注意すべきポイントを解説します。
◎光害防止の基本と岐阜県の考え方
岐阜県は、照明について 、防犯や人の活動・作業の安全性を確保しつつ、景観や環境への配慮を心がけるよう呼びかけています。看板照明における光害防止の具体的な配慮事項は以下の通りです。
- 眩しさの抑制(グレア防止): 道路や周辺住宅へ過度な光が漏れないよう、適切な遮光器具を用いる。特に住宅地では、歩行者や車両運転者の視線に配慮し、設置角度を慎重に調整する。
- 上方への光漏れの防止: 夜空を照らさないことは、光害防止の基本です。理想は「フルカットオフ」 タイプの照明器具。光を必要な範囲に的確に配光してくれます。
- 照度・輝度の過剰防止: 環境別の推奨輝度を守ることは、省エネだけでなく光害防止の観点からも極めて重要です。必要以上の明るさは、生態系への悪影響やエネルギー浪費につながります。
- 点灯時間の管理: 深夜帯など不必要な時間帯の点灯は避け、タイマーによる消灯や減光を行いましょう。周辺住民の安眠を妨げず、エネルギーも節約できます。
これらの対策は、環境省が発行する「光害対策ガイドライン」にも詳細が記載されているので、参考にしてください。
◎岐阜県内の主要エリア別 景観条例のポイント
岐阜県内では、県条例に加え、各市町村が独自の景観条例を定めている場合があります。看板を設置する際は、設置場所の特定の市町村が定める規則を必ず確認しましょう。
例えば、高山市では、重要伝統的建造物群保存地区において、看板は木製または同等の質感が求められ、面積の制限もあります。色彩も落ち着いた色調(茶系、グレー系)が基本となります。
◎条例順守と効果的な看板表現を両立させるには
条例を単なる「制限」と捉えるのではなく、地域に溶け込み、ブランドイメージを向上させる「機会」 と前向きに考えましょう。
- 事前の相談と申請は必須: 看板計画の初期段階から、該当する市町村での相談・申請代行の実績がある業者に相談しましょう。これにより、後からの設計変更リスクを減らせます。
- デザインと技術で調和を創る:
- 素材の選択: 木や金属の渋い風合いなど、周囲の景観にマッチした素材を使用することで、高級感と調和を生み出せます。
- 光の質の見直し: 演色性の高いLEDで落ち着いた色味を表現したり、調光機能を活用して適切な明るさに調整したりすることで、環境に配慮した上質な印象を与えられます。
- 地域性の表現: その土地固有の伝統、文化、自然をモチーフやデザインに取り入れることで、単なる規制順守を超え、住民に愛される看板となります。
◇まとめ
看板の照明は看板の視認性を高め、ブランドの魅力をより効果的に伝えてくれるツールとなります。ただし明るさについては、地域への影響や高齢者への配慮を踏まえ、慎重に検討する必要あり。この記事を参考に、看板を引き立てられる照明計画を考えてみて下さい。






