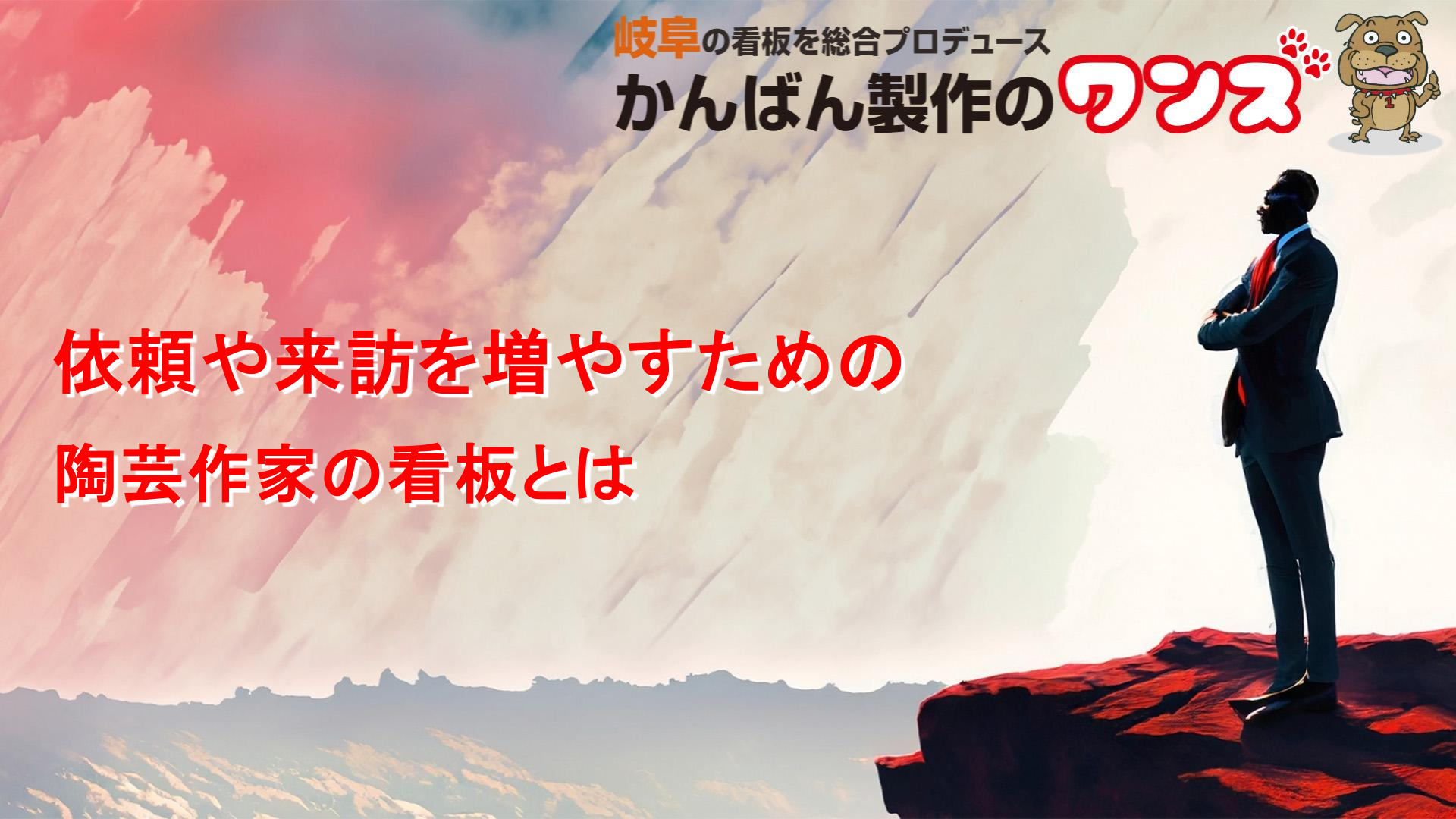
陶芸作品の販売や体験教室など、陶芸作家のビジネスモデルは多彩です。ECサイトでの販売も行われますが、やはり地域に根付き、その土地の文化を反映させた作品が好まれるので、リアルでの商業活動も必須と言えるでしょう。依頼や来訪を増やすために役に立つのが看板です。この記事では、陶芸作家の方が看板を設置する際のポイントについて解説します。
◇なぜ今、陶芸作家にも「看板」が必要なのか?
陶芸作家には凝った看板は必要がないと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし「看板」は作品と同様に「あなたという作家の核を言葉にしたもの」になり得ます。作品の質だけでなく、魅力を伝える力を磨くことで、ファンが選び、応援したくなる作家活動を持続させる土台を作ることができるのです。ここでは、なぜ陶芸作家に看板が必要なのか、理由を深堀します。
◎情報洪水で「ただ良いだけ」では埋もれる!
陶芸作家の魅力発信は「作品の質が全て」と思っていないでしょうか。確かに技術は最も大切ですが、それだけでPRするには現代は「良いもの」が溢れすぎています。
- InstagramなどのSNSやECサイトには国内外の素晴らしい作品が無数に掲載
- 潜在的なファンは「どれを見ればいいか?」と迷い、数秒でスクロール
✅ 解決策:
「◯◯な土と△△焼きで、□□を表現する器作家」など、一言で他の作家と違う「あなたの独自性」を言語化しましょう。それが「看板」の第一の役割です。
◎現代のファンは「ストーリー」で共感する!
特に若い世代や新しいコレクターは、作品そのものより「背景にある物語」に価値を感じる人も多いです。
- 「なぜその形状なのか?」「どんな想いを込めたのか?」に共感が生まれる
- 物語により作品が「単なる器 → 作り手からのメッセージ」に昇華する
✅ 解決策:
プロフィールや作品説明で、
- こだわりの土・釉薬
- 表現したい世界観
をストーリーとして積極的に発信しましょう。
◎信頼と価値が「見える化」で売れる!
特に高額作品やオンライン販売では「顔の見えない作家への信頼形成」が最大の壁です。
- 受賞歴・個展歴・メディア掲載といった実績は「信頼性の証」
- 原料調達・技法・サステナビリティへの姿勢の発信は「こだわりの証明」
✅ 解決策:
ポートフォリオやSNSに「信頼の根拠」を明記!
例:
- 「◯◯産の薬土を使用」
- 「〇〇賞 入選」
「看板」が作品の価値を裏付けるある種の「保証書」になるのです。
◇「らしさ」が伝わる看板デザインの考え方
「看板」の重要性がわかっても、「どうデザインすれば自分らしさが伝わるだろう?」と悩むかもしれません。「デザイン」は見た目が良ければいいわけではなく、あなたの創作の本質を可視化するプロセスを考える必要があります。ここでは3つのポイントに分けて解説します!
◎視覚で伝える:「作品の息吹」をデザインに込める
有名ブランドのリサ・ラーソンのように「見た瞬間にあなたの作品とわかる」デザインが理想です。
- 色:作品の釉薬の特徴(例:灰釉の渋み=濃いグリーン系、染付の青=藍色)
- 形:作風のイメージ(有機的な曲線=手書きフォント、鋭い造形=シンプルな幾何学)
- 素材感:
- 土の質感(ざらざら=クラフト紙背景/つやつや=光沢紙)
- 焼成の特徴(薪窯のスス=黒をアクセントに)
✅ 改善案:
自身の作品写真を並べ「共通要素」を抽出!
「温かみ」「力強さ」「繊細さ」などのキーワードを見つけ、
デザインの基調色やフォントに反映させましょう。
◎ストーリーで紡ぐ:「コンセプト」をデザインで具現化する
ロゴやフォント選びはあなたの創作思想を象徴する最も重要な要素です。
- 自然と向き合う作家
→ 手書きの優しい印象のロゴ・植物や波をモチーフ - 哲学や社会への訴えを表現する作家
→ コンストラクティブなデザイン・モノクロ基調
✅ 改善案:
「私の陶芸は〇〇と△△の融合」と定義し、デザインに反映させると考えやすいです。
◎一貫性で響かせる:全タッチポイントで「世界観」を統一する
SNSやECサイト、名刺、個展ポスターなどすべての媒体で「同じ世界観・空気間」を醸し出すことが作家としての信頼を生みます。
- フォント3択ルール:
タイトル用・本文用・アクセント用を固定しましょう。 - カラーパレット:
ばらばらと色を多用しないように、基調色1+サブ色2+アクセント色1で統一しましょう。
✅ 改善案:
Canvaで「ブランドキット」を作成!
このソフトでロゴ・フォント・カラーを登録すれば、全ての素材でスタイルが自動統一されます。
◇制作依頼や教室案内に必要な情報の見せ方とは
「問い合わせが来ても詳細が伝わらず反応がにぶい…」「教室の申し込みが思ったより少ない」そんな経験はありませんか。情報は「書いてある」だけでは意味がありません。見せる”順番”と”切り口”で成果が決まります。ここでは作品の制作依頼や教室案内に必要な情報の見せ方を解説します。
◎制作依頼編:プロの信頼を築く「3つの必須情報」
制作依頼で重要なのは「この作家さんに何としても頼みたい」という確信を与えることです。掲載すると特に効果的なポイントを厳選してみました:
✅ 絶対に明記すべき3情報
- 📅 納期目安と空き状況
例:「現在〇ヶ月待ち」(予約制の場合)/「相談可」
→ 依頼者が最も気にする「いつ届くか」を最初に記載すると良いです。人気も伝わります。 - 💰 価格帯の明確な提示
例:「湯呑み1客 ¥8,000~」(「〜」を忘れずに)/「◯万円からのオーダー制」
→ 「予算オーバー?」の不安を解消できます。
⚠️ NG例:
「お問い合わせください」だけの案内ではハードルが高いです。問い合わせを減らさないために、顧客の立場に立った情報発信を心掛けましょう。
◎教室案内編:初心者の不安を解消する情報構成
教室の集客力を高める情報発信の鍵は「未経験者でもできる」と確信させる内容を伝える事です。不安を解消し、安心感を与える情報を積極的に記載して下さい。
✅ 申し込みを促す黄金フロー
- **不安解消 →** 「初めてでもたったの2時間で完成!」
(手ぶらOK・焼き上がり後に郵送します)
2.**具体像提示 →** 「作れる作品例」を写真で3パターンほど提示
(※うますぎる作品だけでなく、ほどよい手作り感のある失敗作も添えるとリアルさがUPします)
- **流れ明確化 →** タイムライン図解:
[受付→成形→削り→絵付け→焼成→郵送]のように教室での作業工程を明確にすると不安が和らぎます。
- **特典演出 →** 「当日Instagram用写真サービス」
映える写真の撮影までをセットにするなど、SNS拡散を誘導するアイデアを掲載するのも集客力向上に繋がります。
◎共通ルール:迷いを生まない「情報デザイン3原則」
看板をはじめ、紙でもWebでも使える「見せる技術」として、下記の3つが挙げられます。
✅ プロが実践する鉄則
- 原則1:フォーカスは1画面に1つ
→ 作品依頼と教室は完全分離で作成しましょう。一つの情報の中で混在させるのは情報発信の効果を下げてしまいます。 - 原則2:文字は3段階に削ぎ落とす
大見出し(8ワード以内) → 要点(20字以内) → 詳細 のように段階ごとにわけて情報を整理しましょう。無駄な情報を削ることにも繋がります。
- 原則3:行動を促す文字は「色・位置・文言」統一
例:全媒体で[青色+右下配置+「予約はこちら」]のように、行動促進の文字を統一しましょう。
◇まとめ
陶芸家にとっても看板での情報発信が大切なことがお分かりいただけましたでしょうか。情報の見やすさは、お客様への思いやりです。なるべく不安を解消し、迷わせないデザインが、信頼と申し込みを生むのです。岐阜県内も陶芸は非常に盛んな地域ですので、可児市近郊などで看板掲載をご検討の際は、ぜひワンズプランニングにお問い合わせください。






