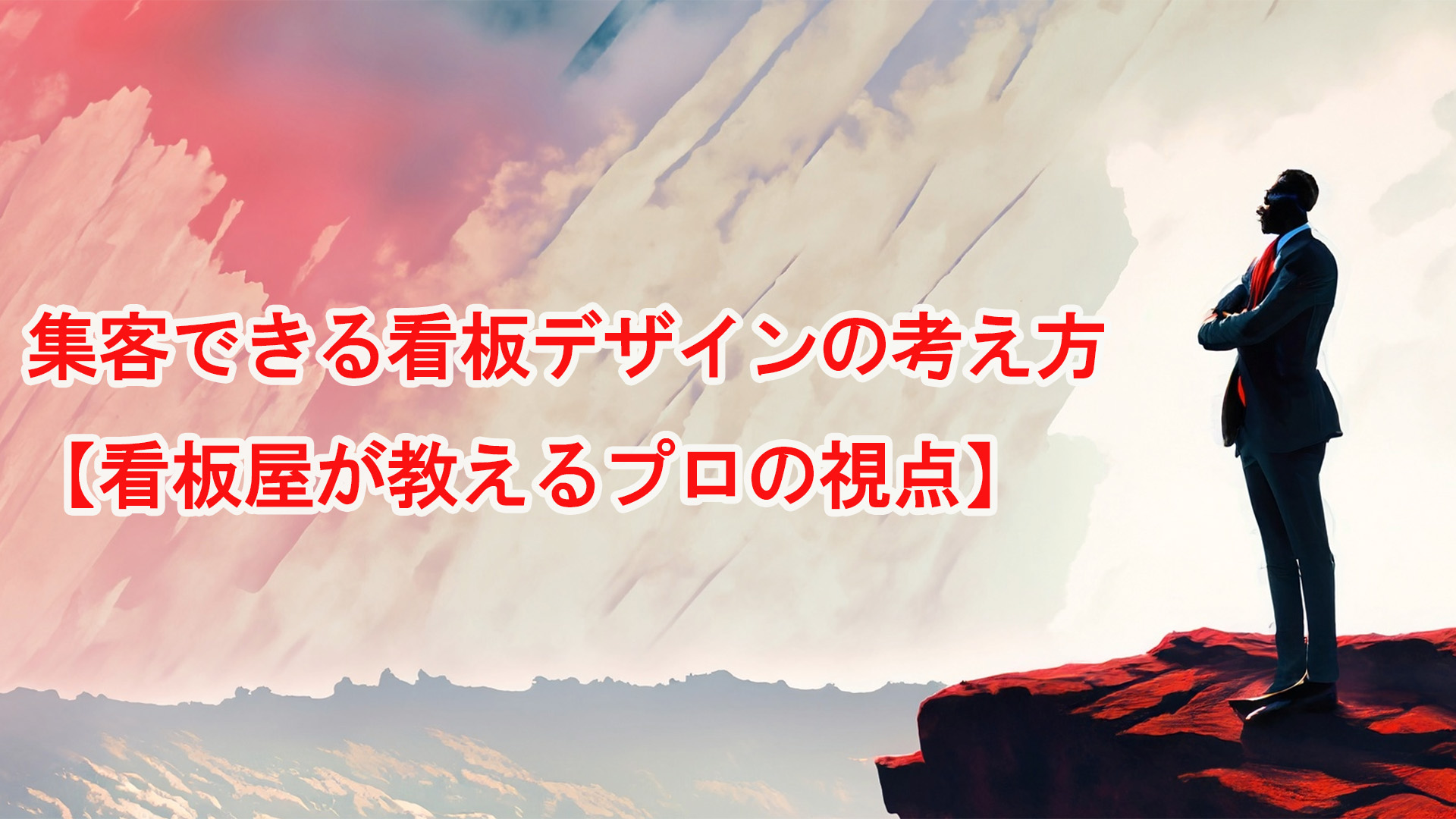
普段の通勤・通学や街歩きの中で、気付かないうちに多くの看板を目にしていると思います。岐阜県内や可児市内の看板でも、はっきりと印象に残るものや、潜在的に記憶に残っているものがあるはずです。店舗や企業のイメージを左右する看板デザインには、集客のために多くの工夫が凝らされています。この記事では、集客につながる看板デザインの考え方について解説します。
◇見る人を引きつける色使いとレイアウトの基本
看板デザインは、店舗の魅力や特徴を伝え、看板を見る人の心を引き付けられるかどうかで効果が大きく変化します。そして、見る人を引き付けるには、色使いとレイアウトで見せ方を工夫する必要があります。ここでは、色使いとレイアウトの基本についてご紹介します。
色の心理効果を活かす:印象を決める配色とは
看板の色は、視覚的にインパクトを与え、目を引くのみならず、顧客の無意識の感情にも働きかけます。これは色彩心理学で説明できる効果で、下記のような例が挙げられます。店舗の印象を強化できる組み合わせを検討しましょう。
- 原色 vs パステルカラー:原色(赤・青・黄)は遠くからでも目立ちやすく、パステルカラーは柔らかで親しみやすい印象を与えます。組み合わせることで、ブランドイメージを強化します。
- 補色と類似色の使い分け:赤と緑など補色の組み合わせはコントラストを強調し、類似色(青と紫など)は統一感を生み出します。
- 業種に合った色選び:飲食店なら食欲を刺激する「赤・オレンジ」が適していますし、医療機関なら「青・白」で信頼感や清潔感を演出しましょう。
POINT:看板単体で考えず、周囲の環境色(建物や風景)とのバランスも考慮し、埋もれない配色を選ぶと良いでしょう。
情報の優先順位を明確にする:レイアウトの黄金比
通行人が看板を見る時間は非常に短いため、情報は「3秒で伝わる」ことが理想です。以下のように視線の流れに沿った配置を意識しましょう。
- Z型or F型レイアウト:人間は自然と左上から右下へ視線が動くという特性を活かし、重要な情報(店名・キャッチコピー)を先に読まれるように配置します。
- 文字サイズの階層化:店名>キャッチフレーズ>詳細情報というように優先度順にサイズを変え、視覚的なリズムを作ります。
- 余白の重要性:情報をあまり詰め込みすぎず、余白を設けることで「読みやすさ」が向上します。
遠くからでも認識できるデザイン:視認性の確保
看板の視認性は「距離」と「時間」との戦いになります。遠くからでも瞬時に内容が伝わる工夫が必要です。
- コントラストの強化:文字と背景の明度差を大きくすることで(例:黒字×黄背景)、視認性を高められます。
- 夜間の照明対策:夜の暗がりでも見えるよう、LEDバックライトや反射材を活用すると良いでしょう。
NG例:薄いピンク地に白文字のような低コントラストでは、昼間にはほぼ読めません。
ターゲット層に合わせたアレンジ:年代・シチュエーション別の工夫
看板の色使いやレイアウトは「誰に」見せるかでデザインを変えることが大切です。
- 若年層向け:ポップな色・イラストでおしゃれ・華やかに。
- 高齢者向け:文字を大きく、色はコントラストを強調。見やすさ重視。
- ドライバー向け:道路の法定速度を考慮し、簡潔な情報に絞る。
応用例:観光地の看板では、多言語表記も効果的です。
◇フォントや文字サイズが与える印象とは
看板デザインでは、上述した色やレイアウトに加え、「フォント(書体)」と「文字サイズ」も重要な役割を担います。小さな一文字のデザインが、店舗の信頼性やコンセプトまでも左右する可能性があるのです。ここでは、フォント選びの基本と文字サイズの最適化について解説します。
フォントが伝える無意識のメッセージ
フォントは人間で言うと「声のトーン」のように、看板の性格を決定づける効果があります。どのようなお店・事業所であるのかを表す良い媒体になります。
- セリフ体(明朝体):
伝統的・高級感・信頼性を表現します。銀行や宝石店に適していると言えるでしょう。逆にカジュアルな飲食店で使用すると堅苦しい印象になります。
- サンセリフ体(ゴシック体):
モダン・親しみやすさ・クリアな印象を与えるフォントです。IT企業やカフェで採用されています。太字は「力強さ」、細字は「洗練されたシンプルさ」を伝える効果があります。
- 手書き風フォント:
温かみ・アート性・個性を強調する字体です。雑貨店やパン屋で使用されます。あまり多用すると読みにくくなるため、短い文言での使用が鉄則です。
文字サイズの「絶対法則」と例外
「遠くから読めるかどうか」は基本的に文字サイズで決まります。以下のポイントを意識して視認性を高めましょう。
- 基本の計算式:
- 文字の高さ(cm)= 看板までの距離(m)× 1.5
- 例:10m先から見える看板 → 最低15cmの文字サイズにする
- 情報の優先度別サイズ分け:
- 店名:最大サイズ(看板面積の20~30%を目安)
- キャッチコピー:店名の50~70%程度
- 住所・電話番号:最小サイズ
- 環境に応じた調整:
- ドライバーに向けた看板:歩行者向けより1.5倍大きく
- 看板の高さ:地上3m以上の場合、下方の文字は見上げるため拡大が必要
業種別・おすすめフォントと避けるべき組み合わせ
業態によって「最適解」が変わります。下記の表は一例です。参考にしてみて下さい。
| 業種 | 推奨フォント | 避けるべきフォント |
| 医療機関 | クリアなサンセリフ細字 | 装飾過多な筆記体 |
| 高級レストラン | セリフ体(明朝系) | ポップな丸文字 |
| 子供向け教室 | カラフルな手書き風フォント | 硬質な角文字 |
| IT企業 | シンプルなサンセリフ中太 | 古風なセリフ体 |
意外な事実:
ファストファッション店では、あえて「手書き風フォント」を使い「手作り感」を演出する戦略も増加しているそうです。
◇看板デザインにありがちな失敗例と対策
看板は「店舗の顔」として重要な役割を担いますが、デザインや設置手法にわずかでもミスがあると、集客効果を低下させる原因になります。初めての看板製作でも、失敗はできるだけ避けたいですよね。ここでは、実際の事例をもとにありがちな失敗パターンと、具体的な解決策を解説します。
視認性の低さ:色とフォントの選択ミス
「思ったより看板が目立たないかも」と設置後に後悔する最大の原因は、色やフォントの選び方にあります。
- 失敗例:
- 背景色と文字色のコントラスト不足(例:薄い水色×白文字)
- 装飾過多なフォントや細すぎる文字
- 夜間の視認性を考慮せず、日暮れ後に読めないデザイン
- 対策:
- コントラスト強化:なるべく明度差の大きい組み合わせ(黒×黄、白×青など)を選ぶ。
- フォント選定:サンセリフ体(ゴシック体)を基本に、文字の太さを調整する。
- 夜間対応:LEDのバックライトや反射材を活用し、24時間視認性を確保しましょう。
情報過多・不足:伝える内容のバランス崩れ
お洒落さやカッコよさにこだわるあまり、「何を伝えるか」の情報選別が不十分だと、看板の目的が曖昧になってしまいます。
- 失敗例:
- 不必要なメニューまで羅列し、全体として文字が小さすぎる。
- 店名のみの記載で「何を売る店か」が初見でわからない。
- 古い価格や期間限定情報を記載し、更新時に看板が陳腐化。
- 対策:
- 3秒ルール:通行人の視線は0.3秒ほどしか留まらないため、メイン情報を10~15文字に絞って最低限の内容を伝えます。
- 階層化:店名>キャッチコピー>詳細情報の順で文字サイズを分けましょう。
- 普遍性:価格や期間限定情報は避け、「代々続く味」など不変の強みを強調すると情報が古くなることを回避できます。
設置場所のミスマッチ:環境分析の不足
立地やターゲット層に合わない場所への設置は、看板の存在意義を失わせます。
- 失敗例:
- 車道向け看板であるのに文字サイズが小さく、運転中に読めない。
- 歩行者向け看板を高い位置に設置し、通行人から視線が届かない。
- 周囲の景色と色が同化し、埋もれてしまうデザイン。
- 対策:
- ターゲット別設計:
- 車向け:標識基準に沿い、文字高さ20cm以上(時速40~60kmの場合)程度に大きくしましょう。
- 歩行者向け:目線の高さ(約1.5m)にスタンド看板を配置すると通行人から見やすいです。
- 環境調査:周囲の建物色や照明を確認し、補色で目立つ配色を選ぶと周囲に埋もれません。
- ターゲット別設計:
デザインと店舗イメージの不一致
看板が店舗のコンセプトと乖離すると、ブランドイメージを確立できないだけでなく、店舗の信頼感を損ないます。
- 失敗例:
- 高級レストランにポップなイラストを使用すると、ターゲット層から悪印象となる場合があります。
- 和食店でモダンな書体を選び、違和感を招くパターンもあります。
- 対策:
- コンセプト統一:
- 業種別フォント例:下記のようにコンセプトと一致させましょう。
- 医療機関→信頼感のあるクリアなサンセリフ体。
- 伝統飲食店→筆書体や明朝体で歴史を感じさせる。
- 業種別フォント例:下記のようにコンセプトと一致させましょう。
- 余白の活用:情報が少ない場合は「店の雰囲気」を表現するデザインに集中(例:高級感なら黒×金)させると良いでしょう。
- コンセプト統一:
◇まとめ
看板のプロは、デザインの色やレイアウト、フォント選択など、細やかな部分まで「いかに集客につながるか」を考えています。業種や店舗のブランドコンセプトによって最適なデザインは異なりますが、デザインを考えていく指針は変わりません。この記事を参考にあなたのビジネスに最適なデザインを検討してみて下さい。岐阜県内や可児市内で看板製作をされる際は、お気軽にご相談ください。






