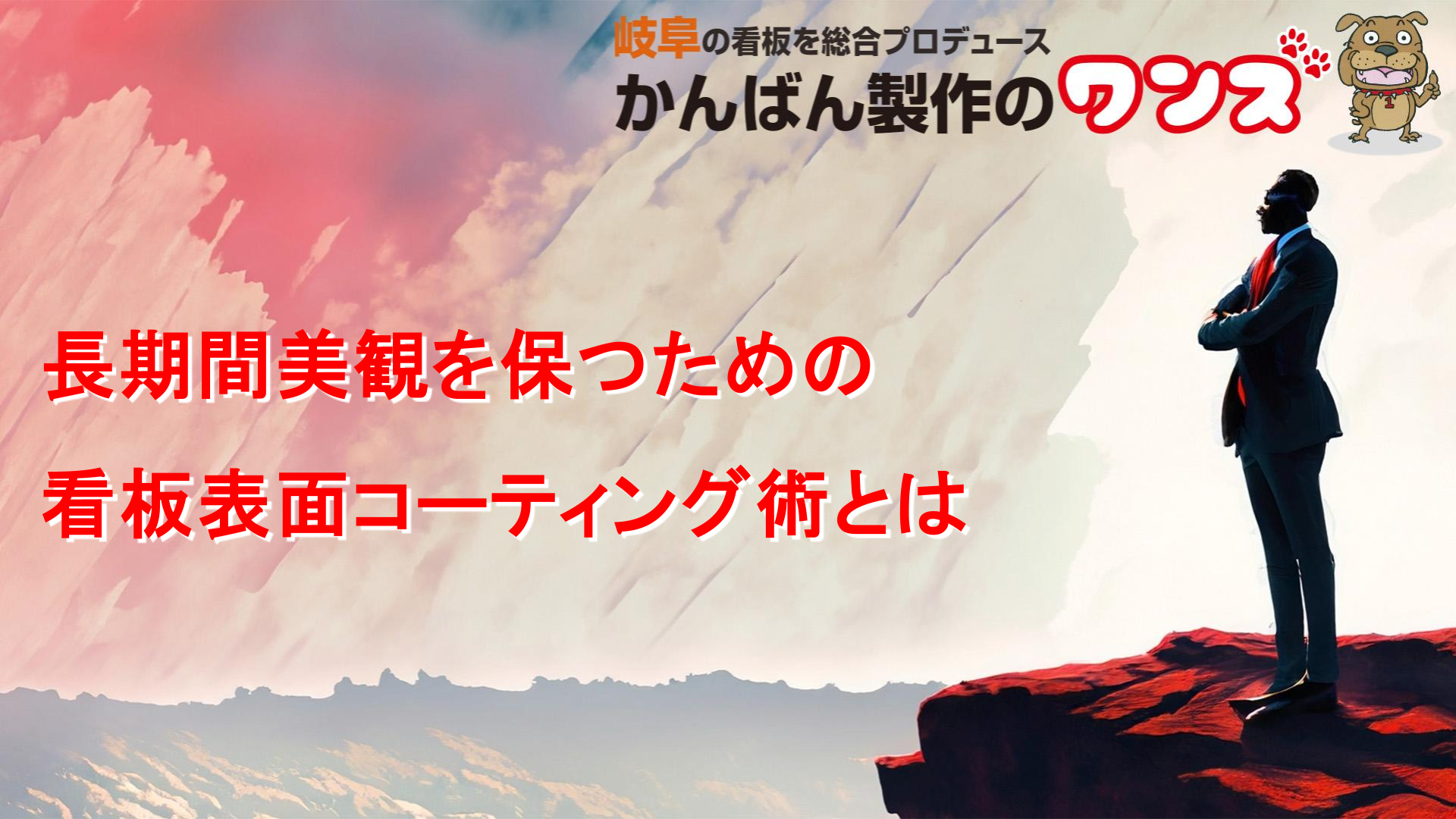
看板は設置後もメンテナンスをしっかりと継続することで初めて集客効果を維持することができます。看板の効果が低下する劣化にはさまざまなものがありますが、一番目立つのは表面の汚れや色褪せ、さびになります。これらのトラブルは、適切なコーティングによって大幅にリスクを減らすことができます。この記事では、看板の美観を長期間保つために必要なコーティングについてご紹介します。
◇UV・防汚・防錆…コーティングの種類と用途
屋外看板は、日光や雨、風など、常に過酷な環境にさらされています。そんな中で長期間美観を保てるよう、耐久性を高めるためには、適切な表面コーティング処理が不可欠です。ここでは、看板の寿命を左右する重要な要素であるコーティングの種類とその役割について詳しく解説します。
◎UV(紫外線)防止コーティング:色褪せを防ぐ守護神
太陽光に含まれる紫外線は、看板のインクや素材を劣化させ、色褪せやひび割れの主要原因となります。UV防止コーティングは、この紫外線を効果的にカットまたは散乱させることができ、看板の色彩を鮮やかなまま保てる期間を延ばします。
コーティングと言えるでしょう。
◎防汚コーティング:メンテナンスコストを削減する工夫
ほこりや排気ガス、油分などの汚れが看板表面に付着すると、美観が損なわれるだけでなく、素材そのものの破損を早める原因になります。防汚コーティングは、汚れを付着しにくくし、付着しても雨風で流れ落ちやすい(親水化または撥水化)性質を与えるものです。
フッ素樹脂コーティングや光触媒コーティングがその代表です。フッ素樹脂は撥水性に優れ、汚れをはじきます。光触媒は太陽光のエネルギーで有機汚れを分解する自己洗浄効果が期待できます。交通量の多い道路沿いや飲食店の看板などに適しています。
◎防錆(さび止め)コーティング:金属看板の寿命を決定する鍵
鉄やアルミニウムなどの金属製看板にとって、最大の敵は「錆(さび)」でしょう。水分や酸素に素材が触れることで化学反応が起こり、見た目が悪化するだけでなく、強度も著しく低下します。防錆コーティングは、金属表面を保護膜で覆うことで、腐蝕環境から遮断し、錆の発生を根本的に防ぎます。
下地処理として化成処理(リン酸塩皮膜処理など)を行い、その上からエポキシ樹脂などの密着性の高いプライマーを塗布。最後にトップコートを重ねるのが標準的な工程となります。海辺など塩害が想定される地域では、より高度な防錆処理が必要でしょう。
◇下地処理が寿命を決める—足付け・脱脂の基本
優れたコーティング材も、下地処理が不十分であればその性能は低下してしまいます。看板の長寿命化において、実は下地処理が非常に重要であると言われるほどです。ここでは、美観と耐久性の土台を築く、下地処理の基本工程である「脱脂」と「足付け」に焦点を当てて解説します。
◎成功の鍵は「脱脂」にあり:油分除去の徹底
看板の表面には、加工段階での切削油や、輸送・設置時に付着した手アカ、自然環境の油分など、目には見えない油脂が存在します。これらを除去しないままコーティングをしてしまうと、塗膜の密着性が著しく低下し、剥離や浮きの原因となります。
脱脂作業では、専用の脱脂剤を用いて表面を徹底的に洗浄します。具体的には、溶剤による拭き取りや、アルカリ性脱脂剤を用いた洗浄が一般的です。特に、複雑な形状のパーツや鋲(びょう)部分などは脱脂が行き届きにくいため、細部まで意識した作業が求められます。脱脂後は、必ず清浄な布やウエスで拭き上げ、シンナー等で仕上げするのが匠の仕事です。
◎「足付け」で確固たる土台を:密着性を高める処理
「足付け」とは、コーティング材の密着性を高めるための下地調整処理全般を指します。主な目的は、コーティング材がしっかりと看板に「食いつく」ことができる表面状態を作り出すことです。
金属看板では、サンドブラストやケミカルコンバージョン処理と呼ばれるものが該当します。これらの処理により、表面に微細な凹凸(アンカーパターン)を形成したり、塗膜との親和性が高い化学皮膜を生成したりします。プラスチック看板では、表面をわずかに粗くするサンディングや、密着性を向上させるプライマーの塗布が「足付け」処理の役割を果たします。
◎下地処理を怠るとどうなる?:よくある失敗例
適切な下地処理を省略したり、いい加減な作業で済ませたりすると、どのような不具合が発生するのでしょうか。下記が主な例です。
- 塗膜の剥離(はくり):最も代表的なトラブルです。経年とともに剥離が進み、大きな膜剥がれを起こします。
- クレーター(はじき):表面に残った油分やシリコーンが原因となり、塗料が均一に広がらず、クレーター状の窪みができてしまうことがあります。
- 錆の蔓延(さんぱん):金属看板で、事前のさび取りが不十分な場合、塗膜の下から錆が進行する「裏錆」現象が起き、最終的に塗膜が浮き上がるトラブルが発生します。
これらは、一度発生すると修復が非常に困難です。美観を損なうだけでなく、看板そのものの早期交換が必要となり、大きなコスト負担にも繋がります。
下地処理は地味な工程ではありますが、看板の寿命を根本で支える大切な作業です。
◇再コート周期とコストの目安・判断基準
美観を保つコーティングは非常に有用ですが、永遠に続くわけではありません。適切なタイミングでメンテナンスを続けることで、看板の寿命をさらに延ばします。ここでは、再コートの必要性を見極める判断基準と、コスト・周期の目安について、具体的な数字を交えながら解説します。
◎コストと作業周期の大まかな目安
コーティングのメンテナンスコストと周期は、看板のサイズや素材、設置環境などによって大きく異なります。あくまで一般的な目安としてご覧ください。
- 周期の目安: 高品質なコーティングを施工した場合、その効果が持続する期間はおおむね5年~10年が一つの目安です。ただし、沿岸部や直射日光が極端に強い環境などでは、3年~5年で再コートが必要になる可能性もあります。
- コストの目安: 費用は「下地処理の有無・程度」と「使用するコーティング材」で大きく変わります。既存塗膜の剥離やサンドブラストが必要な大規模なメンテナンスの場合、新品の看板価格の3~5割程度の費用がかかることもあります。一方、下地の状態が良好で上塗りだけの更新であれば、1~3割程度に抑えられる場合も。いずれにせよ、複数業者に見積もりを依頼し、なぜその費用がかかるのかの説明を求めることがポイントです。
◎メンテナンスコストを抑えるための心得
長期的なコストを削減するには、初期投資と定期点検が鍵です。
- 初期投資の重要性: 設置時に、下地処理にコストをかけ、最高品質のコーティングを施すことは、後のメンテナンス周期を長くします。結果的にトータルコストを圧倒的に安くするので、「安物買いの銭失い」を避けましょう。
- 定期点検の習慣化: 年に1回、専門業者に点検を依頼するのが理想的です。自分自身でも少なくとも2年に1回は目視検査を行い、小さな異常を早期発見しましょう。大規模な修復工事を防げます。
- 部分補修の選択肢: 錆や剥がれが一部だけの場合、全面を再コートするのではなく、部分補修で対応できる可能性があります。業者に相談してみましょう。
◇まとめ
適切なコーティングを選択することは、看板への初期投資を長期的に回収するための大切なポイントです。設置環境や素材をよく考慮し、最適なコーティング技術を採用しましょう。看板は「設置して終わり」ではなく、変化し続けるものです。定期的なメンテナンスは、コストがかかりますが、お店や企業の顔を美しく保つための重要な「投資」といえます。この記事が、皆様の看板を長期的に活用するための一助となれば幸いです。






