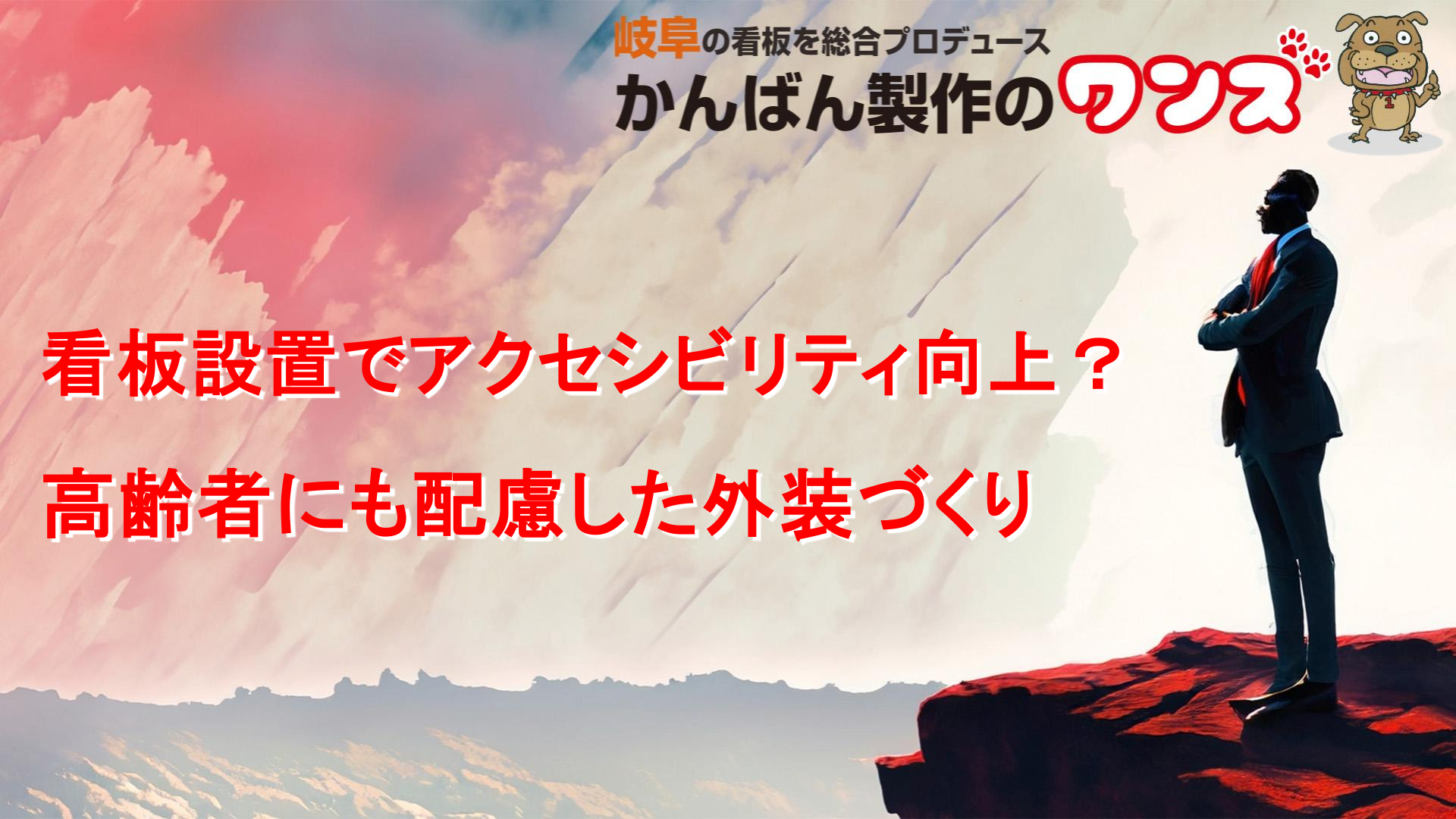
お店の看板やメニュー表を一新する時、どのような点を考慮してデザインをイメージされますか?「おしゃれで洗練されたデザイン」ももちろん素敵ですが、それだけで終わらせていませんでしょうか。店舗にとって、看板はお客様を迎える最初の「顔」です。その顔が、ご高齢の方をはじめとした特定の人たちにとっては「見えにくい」ものだったら、せっかくの集客のチャンスを逃しているかもしれません。この記事では、看板のアクセシビリティに焦点を当て、外装作りのポイントを解説します。
◇高コントラスト配色と大きめフォントの基準
アクセシビリティとは、利用しやすさのことです。これを高める外装づくりの基礎となるのが、「色」と「文字」。ここでは、高齢化社会において必須の視点と言える、配色とフォントの配慮すべきポイントについてご紹介します。
◎なぜ「高コントラスト」が重要なのか?
人間の目は加齢に伴い、水晶体が濁ってくると、光が散乱してコントラスト感度が低下します。つまり、色と色の境目がわかりづらくなり、「灰色の文字と薄いベージュの背景」といったような低コントラストの組み合わせは、ほとんど認識できなくなってしまうのです。
これを解決するのが「高コントラスト配色」。最も認識しやすい組み合わせは、白と黒でしょう。しかし、それだけではデザインが単調になりがちなので、以下のような組み合わせも効果的です。
- 黒/濃い青 × 白
- 白 × 濃い赤
- 深紅 × クリーム色
逆に、避けるべきなのは明度(明るさ)が近い色同士の組み合わせです。赤と緑、ピンクと水色などは、色覚の特性によっては判別が難しい場合もあります。
◎具体的な数値で知る「見やすい文字の大きさ」
「大きめのフォント」という曖昧な表現では、適切な配慮はできません。では、どれくらいの大きさが必要なのでしょうか?
歩行者が数メートル先から確認する主要な情報(店名など)には、最低でも視認距離の1/200の大きさが推奨されています。つまり、5メートル先から見えるようにするには、5m ÷ 200 = 2.5cm 以上の文字の高さが必要です。メニューなど近距離で見る文字でも、基本的に1cm以上は確保したいところです。
◎フォント選びのちょっとしたコツ
大きさだけでなく、書体(フォント)の選択も重要です。
- ゴシック体が基本:線の太さが均一で、すっきりとしているゴシック体やサンセリフ体は、高齢者に優しく、遠くからでも認識しやすいです。
- 極太字体や極細字体は避ける:極太字体はかえって文字がつぶれ、読みにくくなってしまいます。極細字体は背景と同化し、視認性が下がる可能性があります。
- シンプルなデザイン:装飾が多すぎる書体や、線が複雑に絡み合う筆記体は、視認性が落ちるので控えめに。
◇段差・手すり・導線を意識したサイン計画
前章で「見やすさ」の重要性についてお話ししました。しかし、せっかく看板がよく見えても、顧客がスムーズに店内にたどり着けなければ意味がありません。特に高齢者や足腰の不安な方にとって、ほんの小さな段差やわかりづらい導線が、大きな心理的・物理的バリアになり得ます。ここでは、誰もが安全かつストレスなく移動できるための看板を活かした環境づくりについて考えます。単なる情報発信のツールではなく、顧客を導く「道標」として機能させることを目指しましょう。
◎危険箇所の事前チェックと注意喚起サイン
まずは、店舗の外回りから入口までを顧客の目線で歩き、危険な箇所がないか徹底的にチェックしましょう。特に以下のポイントは要注意です。
- 駐車場や歩道にあるわずかな段差
- 舗装の凹凸や溝
- タイル張りなど雨の日に滑りやすい床
これらの物理的なバリアは完全に無くすことが理想ですが、現実的には難しい場合も多いでしょう。そんな時は、「注意を促すサイン」 が妥協案になります。段差の手前には足元注意を促すピクトグラム(絵記号)、滑りやすい場所には「すべりやすいのでご注意ください」などの温かい言葉を添えた看板を設置しましょう。サインの色は黄色と黒の警戒色を使うことで、視覚的に危険を伝えることができます。
◎安心を生み出す「手すり」のススメ
段差を完全になくせない場所、例えば店舗へのアプローチに数段の階段がある場合、最初の解決手段となるのが手すりの設置です。手すりは単なる体の支えではなく、心理的な安心感を与える「命綱」のような役割を果たします。
手すりを設置する際のポイントは2つです。
- 両側設置が理想:利き手や身体の状態は人それぞれです。可能であれば階段やスロープの両側に手すりを設置することで、より多くの方に対応できます。
- 太さと素材:握りやすい太さ(直径3.5cm程度)が重要。夏は熱くならず、冬は冷たすぎない(木や樹脂製など)素材が理想的です。
◎迷わないための「導線デザイン」とサインの連続性
顧客を迷わせないことは、最高のおもてなしの一つです。そのためには、導線上にサインを切れ目なく配置する「連続性」 が鍵になります。
- 目的地まで一貫した表示:離れた場所の駐車場なら「入口はあちら→」のように標識を設け、その先の分岐点にも設置することで、最終的に入口にたどり着けるようにします。
- 視点の高さを考慮:車いすの方やお子様の目線も考慮し、低めでも見やすい高さに設定しましょう。高い位置と低い位置の両方に同じ情報を表示することが理想的です。
- シンプルで直感的なピクトグラム:トイレや非常口のピクトグラムなど、言葉がなくても理解できるロゴを積極的に活用しましょう。
◇眩しさ・反射を抑える素材と表面仕上げ
どれだけ優れたデザインの看板にも、台無しになるリスクがあります。それは太陽光や店内の照明による乱反射。特に高齢者は光の散乱による「眩しさ(グレア)」に敏感であり、コントラスト感覚も低下するため、反射があると文字や情報が一層読み取りづらくなってしまいます。ここではアクセシビリティを高める手法として、看板の「素材選び」と「表面処理」にスポットを当てます。適切な素材選びは、情報の視認性を確保するだけでなく、店舗の高級感まで左右する重要な要素です。
◎なぜ「眩しさ」と「反射」が問題なのか?
加齢に伴い、目の水晶体が濁ると光が散乱しやすくなります。これにより、以下のような問題が発生します。
- 白色現象:看板表面の光が乱反射し、文字や背景が白く曇ってします。コントラストが大幅に低下する。
- まぶしさ:直射日光や照明が看板に反射すると、まぶしすぎて、看板を見ようとする意欲が削がれてしまう。
- 映像の映り込み:光沢のある表面に周囲の風景や人物が映り込み、看板の情報を覆い隠してしまう。
これらの問題は、せっかく大きくてコントラストのはっきりした看板の効果を半減させ、場合によっては全く読めない状態にしてしまいます。
◎効果的な素材と表面処理の選び方
反射と眩しさを抑えるためには、光を拡散して跳ね返す「マット(つや消し)調」の素材使用や加工が非常に有効です。
- 看板のベース材:光沢のあるアクリル板やガラスではなく、拡散性の高いマット調のアクリル板や天然木材(表面はつや消し塗装) などを選びましょう。
- 文字の素材:光るステンレスの文字は、太陽の方向によっては強烈な反射を生み出します。マットな樹脂製の文字や、つや消し塗装を施した金属文字がおすすめです。
- 表面加工:看板全体を保護するための表面カバーにも注意が必要です。光沢のあるビニールシートではなく、ノングレア(防眩)加工が施されたフィルムを貼ることで、反射を大幅に抑えることが可能です。
◎照明計画と設置場所との連携
素材選びは、看板を「どこに」「どのように」設置するかという照明計画とセットで考える必要があります。
- 直射日光を避ける:看板の設置場所を選ぶ際は、一日のうちどれくらい太陽光が直接当たるのかを考慮しましょう。なるべく反射しない時間帯に太陽光が当たるように考慮し、ひさしをつけるなどの物理的な対策が有効です。
- 照明は「照らし方」も大事:看板を内部から照らす内照式看板は夜間に非常に目立ちますが、昼間は表面で光が反射して見えにくくなる場合があります。外側から斜めに照らす「外部照明」の方が、素材の影響を受けにくい可能性も。照明の角度を調整し、視認者に直接光が当たらないように配慮しましょう。
◇まとめ
「おしゃれ」と「見やすさ」は必ずしもトレードオフの関係ではありません。コントラストと文字サイズの基準を守った上で、自店の世界観に合った書体やアクセントカラーを探してみましょう。ほんの少しの気遣いが、お年寄りから「見やすくて助かる」と感謝される、温かいお店づくりの第一歩になります。ワンズプランニングは岐阜県内や可児市内でアクセシビリティの高い看板づくりに取り組みます。お気軽にご相談ください。






