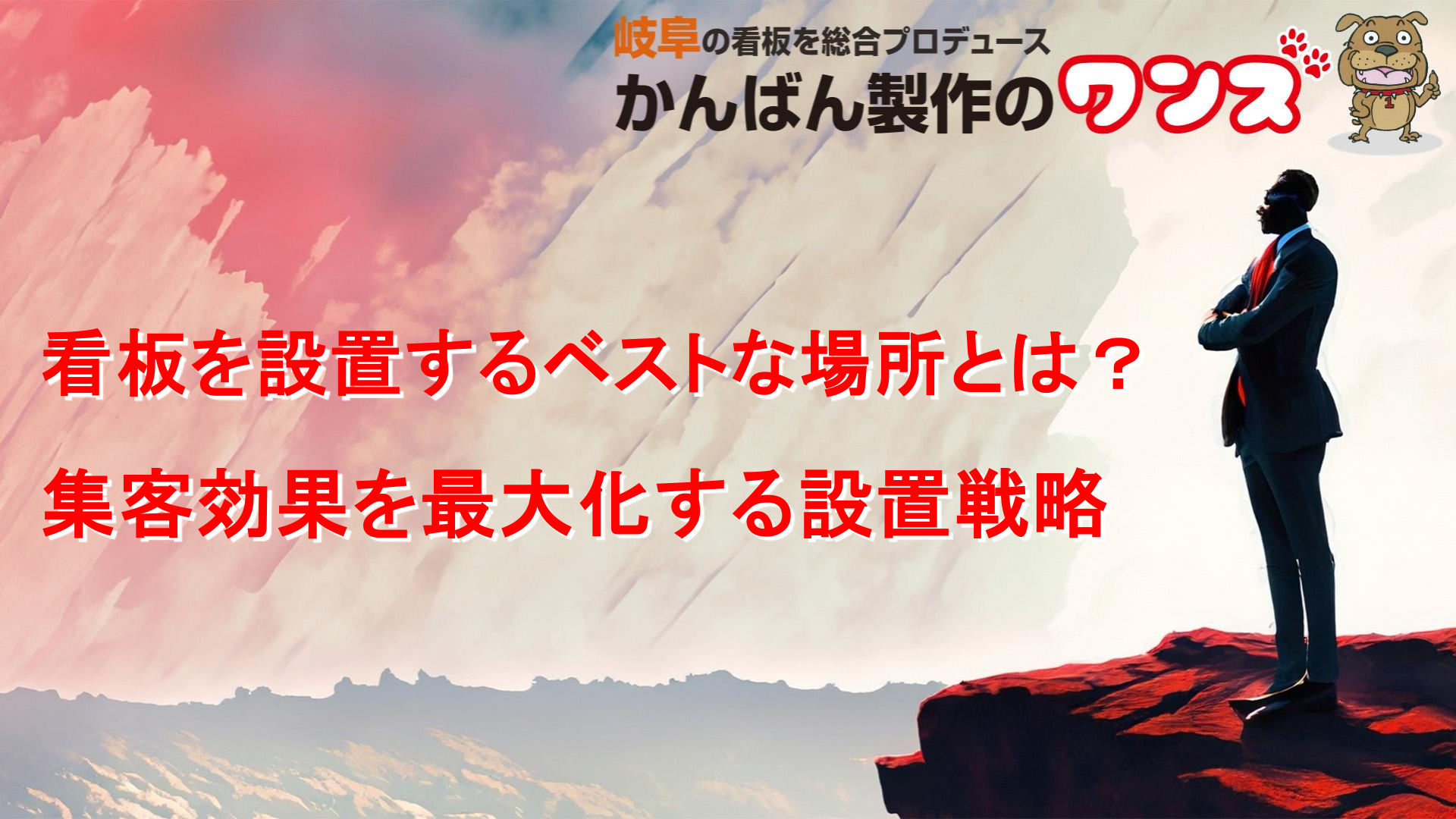
どこにでも見かける看板ですが、実は設置場所も集客効果に対する影響が非常に大きい要素です。せっかくこだわり抜いた質の高いデザインを作れても、設置場所で失敗してしまうと十分な効果を得られない可能性が高いです。この記事では、これから看板の制作を検討している方に向け、ベストな設置場所の考え方をご紹介します。
◇主導線を見極める──歩行者/ドライバー別の視線と滞留時間の分析
看板を効果的に設置するためには、通行人の動線と視線を理解することが不可欠です。歩行者とドライバーでは、視線の向け方や看板付近での滞留時間が大きく異なります。ここでは、それぞれの特徴を分析し、看板設置のベストな場所を探ります。
◎歩者の動線と視線の特徴
歩行者は比較的自由な動線を持ち、周囲を広く見渡す特性があります。視線は一定ではなく、スマートフォンを見たり、他の通行人に注目したりと分散しがちです。歩行者の平均的な滞留時間は短く、看板を見る時間は数秒程度と言われています。そのため、歩行者の自然な視線の流れを意識し、かつ短時間で情報を伝えるデザインが求められます。歩行者が多いエリアでは、目線の高さに合わせた設置や、動線を考慮した角度が鍵となります。
◎ドライバーの動線と視線の制約
ドライバーの視線は前方に集中するのが基本であり、看板に注目できる時間はさらに短くなります。標識や信号、他の車両など、注意を払う対象が多く、看板はあくまで視界の一部でしかありません。また、速度によっても認識できる時間が変わり、高速道路ではより一瞬の判断が求められます。ドライバー向けの看板は、簡潔で視認性の高い情報を、運転を妨げない位置に設置する必要があります。
◎最適な看板設置のポイント
歩行者とドライバー、双方に効果的な看板にするためには、以下のポイントを押さえましょう。まず、ターゲット層を明確にし、それに合わせた設置場所とデザインを選ぶこと。歩行者向けなら細かい情報も掲載が可能ですが、ドライバー向けは極力シンプルにしましょう。また、滞留時間の短さを考慮し、一目で理解できるメッセージに仕上げる事も大事です。立地によっては、歩行者とドライバーの両方に見てもらう必要がある場合もありますので、異なる角度からでも認識できるよう、複数の看板を組み合わせるなどの工夫が求められます。
◇視認距離と文字サイズの関係──10m・30m・50mで読ませる設計のコツ
看板の情報を確実に伝えるためには、距離に応じた適切な文字サイズの設定が不可欠です。歩行者とドライバーでは接近速度や認知時間が異なり、視認性を確保できる文字サイズも変化します。ここでは、10m・30m・50mという代表的な距離別に、看板を確実に読ませる設計のコツを解説します。
◎近距離(10m)の看板──歩行者への細かい情報伝達
10mという距離は、歩行者が詳細な情報を得るのに最適な範囲です。これくらい近ければ、ある程度の長文や細かい数字も認識できます。文字サイズの目安は、最低でも上下に3cm以上を確保しましょう。ただし、歩行者は必ずしも看板に正面から向き合うとは限りません。斜めからでも認識できるよう、太めの書体や十分な行間を取ることも意味があります。
◎中距離(30m)の看板──車両からの視認性を考慮
30m先の看板は、車両が減速したり停止したりする機会に目にする距離です。例えば交差点や信号待ちの地点など、ドライバーが数秒間注目できる環境を想定します。文字を読むためには、文字の高さが少なくとも10cm以上必要でしょう。看板全体のサイズも大きくし、情報は極力簡潔に。キーワードを大きく強調する、絵やイラストを併用するなどの工夫で、瞬時の理解を助けます
◎遠距離(50m)の看板──高速走行時の認識を確保
50mという距離は、高速道路や自動車の流れが速い道路を想定します。詳細な情報を読むことはほぼ不可能であり、看板は極めて短い時間しか視界に入らない状況です。文字の高さは少なくとも20cm以上確保し、情報はブランド名とロゴなど最小限に絞りましょう。さらに、色のコントラストを強くし、遠くからでも目を引くデザインを心がけます。安全を考慮し、多すぎる情報を与えない配慮も必要です。
◇角地・路面店・2階以上など立地タイプ別の最適ポジション
看板の効果は細かな立地条件によって大きく左右されるものです。角地、路面店、2階以上など、それぞれの立地に特有のメリットと課題があります。下記では立地タイプ別に、看板を最大限に活かす設置ポジションのコツを挙げてみました。
◎角地の看板──二方向からの視認性を活かす
角地は二方向からのアプローチがあるため、看板設置において有利な立地の一つです。しかし、単に角地に設置すればいいわけではなく、歩行者やドライバーが交差点を曲がる際の自然な視線の流れを考慮することが重要です。曲がり角の手前側に看板を設置することで、減速中のドライバーや方向転換する歩行者の注意を引きやすくなります。また、看板を斜めに設置すれば、両方向から認識しやすくなります。
◎路面店の看板──歩行者の視線を捉える技術
路面店では、歩行者の動線と視線を詳細に分析することが看板の効果を高めます。看板は歩行者の目の高さ(通常は約150-160cm)に合わせ、歩行方向から自然に視界に入る角度に設置しましょう。店頭看板(サインボード)は、遠くからでも店舗の存在が分かるよう、十分な高さと大きさを確保することが必要です。夜間の営業がある業種では、看板の照明やスポットライトにより、暗がりでも目立つように配慮しましょう。
◎2階以上の看板──上方への視線誘導を工夫する
2階以上に店舗がある場合、「いかにして上方に視線を向けさせるか」が鍵になります。地上から見上げたときに読みやすいよう、看板はやや俯き気味に設置するのがコツです。ビルの壁面を使った縦長看板は、上方に店舗があることをアピールするのに有効です。また、1階の入口部分、または階段やエレベーターの付近に補助看板を設置するなど、顧客をスムーズに店舗まで導く工夫が必要です。
◇岐阜エリアでの設置許可・景観配慮の基本チェックポイント
看板設置において、効果的な集客と地域との調和を両立させるためには、法令遵守と景観への配慮が不可欠です。岐阜県は豊かな自然資源と歴史的街並みを有する一方、開発行為や工作物の設置には一定の規制が設けられている地域もあります。本章では、岐阜エリアで看板を設置する際に押さえるべき基本チェックポイントを解説します。
◎開発行為と看板設置の法的規制
看板の設置において、特に大規模なものや基礎工事を伴う場合は、開発行為に該当する可能性があります。岐阜県では、都市計画法に基づき、一定規模以上の開発行為には許可が必要となります。
開発許可が必要な主なケース
- 開発区域の面積が1,000㎡以上の場合(市街化区域か市街化調整区域かによって要件は異なります)。
- 開発行為が盛土規制法に定められた工事(例えば、高さ5mを超える擁壁の設置など)に該当する場合、面積によってはさらに厳格な基準が適用されます。
申請の流れと注意点
- 申請窓口: 開発行為の許可申請は、原則として市町村の担当窓口を経由して提出します。ただし、岐阜市(中核市)や大垣市、高山市、多治見市、各務原市、可児市(事務処理市)では、それぞれの市が独自に許可事務を行っているため、これらの市域内においては直接市へ問い合わせる必要があります1。
- 標識の掲示: 開発許可を受けた工事では、許可内容等を記載した標識の掲示が義務付けられています。盛土規制法の工事に該当する場合は、それに関する標識の掲示も必要です1。
◎道路占用と工事の許可申請
看板を道路や歩道に設置する(占用する)場合、道路管理者(県や市町村、国道事務所など)の許可が求められます。
道路占用許可
- 看板を公道の上空に設置する場合、道路占用許可の申請が必要です。
- 申請の際は、看板の構造や設置方法が道路法や関連する基準に適合していることを示す書類を提出せねばなりません。
◎岐阜の景観特性に配慮した看板設計
岐阜県は、世界遺産・白川郷をはじめとする重要伝統的建造物群保存地区、清流長良川といった豊かな自然、城下町の面影を残す歴史的な街並みなど、多様な景観資源に恵まれています。看板設置に際しては、目立たせることを目的にすると周囲から浮いてしまう可能性も。地域特性を尊重し、景観を損なわない配慮が強く求められます。
景観配慮のチェックポイント
- 規模・高さの抑制: 周囲の建物や自然環境に圧迫感を与えないよう、過度に巨大な看板や高い看板は避けるべきです。
- 色彩・デザインの調和: 街並みになじむ伝統色や素材感を考慮し、派手すぎる色彩や周囲と調和しないデザインは控えましょう。歴史的町並みや自然豊かなエリアでは、落ち着いたトーンや自然素材の活用が好まれる傾向があります。
- 照明の適正化: 夜間の照明は、過度な輝度や光漏れによって近隣住民や動植物に悪影響を及ぼさないよう、適切な配光や調光ができる仕様を選定しましょう。
◇まとめ
看板の効果は、設置場所に大きく左右されることがお分かりいただけたのではないでしょうか。そしてその設置場所から想定される、通行人との距離に合わせた文字サイズと設計が大切です。視認距離を明確にし、それに応じたデザインを採用することで、より多くの人に情報を届けることができるでしょう。視線の流れや動線を考慮した設置ポジションを選ぶことで、看板の効果を最大限に高めるはずです。岐阜県内や可児市内で看板の設置場所を検討されている方は、ぜひワンズプランニングまでお声かけ下さい。






