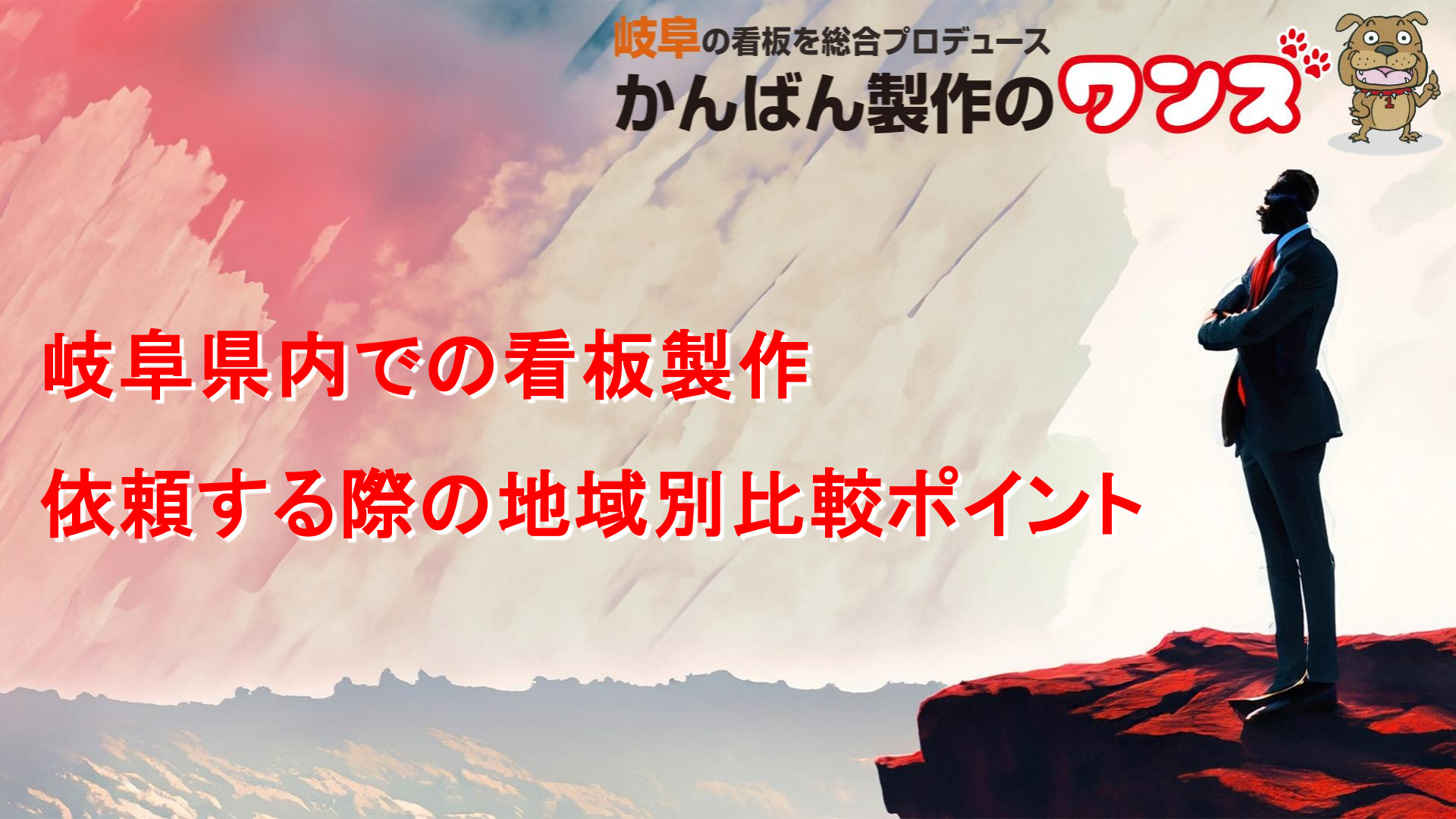
効果的な看板デザインにはある程度共通する部分がありますが、一般的に〝良いデザイン〟と呼ばれるクオリティに仕上げても、必ず成功するわけではありません。看板の設置場所・地域には特性があり、それら外的要因を踏まえて看板製作を依頼する必要があるのです。この記事では、岐阜県内を例に挙げ、看板づくりを行う際に場所や地域ごとに検討すべきポイントについて解説します。
◇風雪・日射・地形など環境条件の地域差
南部と北部で大きく環境が異なる岐阜県内で看板を製作・設置する際には、地域ごとに異なる環境条件を考慮することが不可欠です。豊かな自然と多様な地形を持つ本県では、地域によって風雪害や日射量、地形特性が大きく異なり、これらの要素が看板の耐久性や集客効果に大きな影響を与えます。ここでは、風雪・日射・地形という3つの観点から、岐阜県内の地域差を説明します。
◎気候条件の地域差と看板への影響
岐阜県は内陸性気候で夏の暑さと冬の寒さが厳しいですよね。そして飛騨地方では降雪量が多いことが特徴です。このため、看板の製作や設置には、地域の気候に適した素材選びと設計が求められます。
- 飛騨地方(高山市、飛騨市など):
- 冬季の積雪や凍結といった厳しい気象条件に対応できる耐久性が必要です。看板には、重みや劣化に強い素材・構造が求められます。
- 特に寒冷地では看板の照明や電飾部分が低温の影響を受けないよう、耐寒仕様を検討する必要があります。
- 美濃地方(岐阜市、大垣市など):
- 比較的降雪は少ないものの、夏季の強い日射しと高温、紫外線による影響が看板の褪色や劣化を早めるリスクがあります。
- このため、紫外線に強い塗装を施したり、耐候性の高い素材を採用したりすることが、看板の寿命を延ばすポイントになります。
◎地形と設置場所に応じた対応
岐阜県は南北に長く、山間部と平野部で地形が大きく異なります。看板の効果を高めるには、この地形差を考慮した視認性の確保と安全性の配慮が重要です。
- 山間部や傾斜地:
- 道路が曲がりくねっていることが多く、ドライバーが看板を認識できる時間が限られます。適切な角度と明瞭なデザインが求められます。
- 傾斜地に看板を設置する場合は、基礎工事や土留めなど、安定性を確保するための措置が特に大切です。必要に応じて行政へ許可申請する必要もあります。
- 市街地や平野部:
- 建物や他の看板が密集し、視界の妨げや競合が発生しやすいエリアです。自身の看板が埋もれないよう、適切な高さの確保や照明の活用を考慮する必要があります。
- 歩行者や車両の動線を事前に分析し、自然な視線の流れの中で認識されやすい位置への設置を心がけましょう。
◇幹線道路/駅前など導線別の視認性特性
看板の最も重要な役割は「集客」でしょう。その効果を最大化するためには、店舗まで導く「導線」の役割、すなわち人や車の流れの特性を深く理解することが不可欠です。岐阜県内でも、幹線道路と商店街とでは、人々の動き方や視線の向かう先が全く異なりますよね。ここでは、導線別の視認性特性を理解し、それに合わせた看板製作のポイントを解説します。
◎高速・幹線道路における視認性の確保
東海北陸自動車道や中央自動車道、国道41号線などの主要幹線道路は、高速で走行する車両が主な対象となります。そのため、一瞬で情報を伝えることが最大の課題です。
- 認知時間の短さへの対応:
- 時速60kmで走行する車は、1秒間に約17mも進みます。看板を読み取れるのはほんの数秒であるため、極めて短い時間で理解できるデザインが求められます。
- 具体的には、大きなフォントサイズ、シンプルなロゴ、遠くからでも目を引くコントラストが効果的です。なるべく細かい文字や複雑な地紋は避けるべきです。
- 視点の高さと角度:
- ドライバーの視線は路面から一定の高さにあります。基本的に看板は車の流れに対して直角に設置し、ドライバーの視界を自然に捉える位置(通常はやや上方)に設置することが重要です。
◎駅前・商店街歩行者導線の視認性特性
岐阜駅や大垣駅周辺、高山の古い町並みなどの歩行者導線では、人々は比較的ゆっくりと移動し、周囲を見渡しながら歩くという特性があります。ここでの看板は、詳細な情報を伝え、関心を引く「引き込み」の役割が主となります。
- 詳細情報の伝達と装飾性:
- 歩立ち止まって看板を読む余裕があります。そのため, 営業時間や定休日、主要メニューやキャッチコピーなど、顧客の行動を決定づける詳細な情報を盛り込むことが可能です。
- 店舗の雰囲気やコンセプトを伝える装飾性の高いデザインも有効です。看板自体が街並みの一部となり、魅力を伝えることで、好感度と認知度を高めます。
- 視線の高さと近接性:
- 歩行者の視線は車よりも低く、看板との距離も近いです。それゆえ、ある程度まで細かい情報まで読みやすくデザインする必要があります。
- 看板は歩行者とほぼ同じ目線の高さに設置されることが多く、店頭ののれんや縁看(ふち看板)なども効果的です。
◎車での来店が主体の店舗における導線デザイン
郊外のロードサイド店舗や大型商業施設では、ほとんどの人にとって「車で来て、車で帰る」 という導線が前提となります。よって看板は、ドライバーに対してスムーズな店舗への誘導を行うことが使命です。
- 段階的な情報提示の重要性:
- 幹線道路から認識できる大型のサインで店の存在を知らせ(第1の看板)、店舗入口手前で減速などを促す方向指示看板(第2の看板)、駐車場への進入を案内するピクトグラム(案内用図記号)を設置するなど、段階的に情報を提示することが不可欠です。
- 駐車場内での視認性:
- 看板の役割は店舗入口までで終わりではありません。広い駐車場では、店舗入口の位置を明確に示す看板も重要です。
- 夜間の営業であれば、照明や電飾により視認性を高めましょう。暗がりでもしっかりと認識できる明るさとコントラストが求められます。
◇岐阜市や各務原市、可児市の地域イベントや特性を活かした運用設計
看板は単なる情報伝達の手段ではなく、地域との交流の一環であり、訪れる人々への最初のメッセージにもなる存在です。岐阜県内でも例えば岐阜市、各務原市、可児市では、それぞれの地域特性や多彩なイベントを看板の運用設計に取り入れることで、より効果的で地域に根ざした集客効果を発揮できます。これら3市を事例として、特性を活かした看板運用のポイントを以下に解説します。
◎岐阜市:歴史と伝統を現代に伝える看板戦略
岐阜市は、織田信長ゆかりの地であり、長良川の鵜飼など1300年以上の歴史を持つ伝統文化や岐阜城をはじめとする歴史資産が豊富です。これらの特性を看板に活かすには、歴史的風情と現代的なデザイン性の調和が鍵となります。
- イベントに合わせた動的な看板運用:
- 岐阜市では、例えば4月上旬の「岐阜まつり 道三まつり」、5月の「ぎふ長良川の鵜飼開き」など、年間を通じて大規模なイベントが目白押しです。
- これら主要イベントの開催時期に合わせ、看板のデザインやメッセージを一時的に変更することは注目を集めるのに極めて有効です。例えば、鵜飼シーズン中は看板に鵜匠のシルエットや鵜をあしらったデザイン要素を追加すれば、観光客への強力なアピールとなります。
- 素材とデザインの選定:
- 歴史地区や岐阜城周辺では、看板も景観の一部とみられます。木目調の素材や落ち着いた色合いを採用するなど、周囲の歴史的景観に調和したデザインが求められます。
◎各務原市:市民参加と賑わい創出を促す看板の役割
各務原市では、官民連携によるまちづくりイベントや、市民が主体となった活動が活発です。例えば、「那加デザインミーティング」のようなまちづくりに関する意見交換の場が持たれています。このような市民参加型の地域特性を看板運用に取り入れることで、地域への愛着と集客を両立できます。
- 交流を促進する看板の設置:
- 商店街や公共空間では、地域のイベント情報や市民の活動を発信する「コミュニティ看板」 としての機能を持たせることが有効です。例えば、那加商店街周辺であれば、地域のイベントカレンダーや地元店舗の紹介コーナーを取り入れることで、回遊性と滞在時間の向上に寄与します。
- SNSのハッシュタグを記載し、訪れた人がその場で投稿したくなるようなフォトジェニックな写真スポットを看板と一体で設計するのも、現代的な集客手法です。
◎可児市:文化・自然・体験を一体化した総合的な看板設計
可児市は、戦国城跡(美濃金山城)などの歴史資源や、ぎふワールド・ローズガーデン、可児市文化創造センターalaなどの文化施設といった体験型スポットまで、多様な魅力を併せ持つ地域です。これらの資源を結びつけ、相乗効果を生む看板設計が考えられます。
- 周遊を促す看板ネットワークの構築:
- 例えば、美濃金山城跡と道の駅可児ッテ、荒川豊蔵資料館といったスポット間では、相互に各施設の存在や所要時間、イベント情報を記載した看板を設置し、周遊を自然に提案できるような仕掛けが有効です。
◇まとめ
同じ岐阜県内でも、それぞれ歴史、市民参加、文化・自然体験という強みや気候条件には違いがあります。効果的な看板運用とは、これらの地域特性をデザインや設置方法、運用方法にまで落とし込み、地域の魅力を増幅させる装置として機能させることです。そのためにも、看板を制作する際は地域に詳しい地元の看板製作会社に相談することが大切。より深い洞察と最適な提案を得る上で不可欠です。岐阜県内で看板製作をご検討の際は、ぜひ弊社へお声かけ下さい。






